SEOを意識したサイト運営において、無視できないのが検索エンジンです。
検索エンジンは仕組みをわかっていなくても使えてしまうので、その本質を知らないという人も多いのではないでしょうか?
「 検索エンジンとSEOについてよくわかっていない」という方は、最後まで記事を見ていただけたらと思います。
今回は以下の内容について解説します。
SEOとは何か?

まずはSEOの基本的なポイントについて振り返っておきましょう。
その前に検索エンジンについて解説します。
関連記事:SEOとは
検索エンジンの役割は何か?
私たちが日常的に使っている検索エンジンには、2つの役割があると考えられます。
①知りたい事柄について答えを返す
②多くの人に見てもらう「 場 」を提供する
基本となるのは①です。
私たちは、何かしらの知りたいこと・わからないことがあるので検索エンジンを使っています。
「 あの四字熟語の意味は? 」「 東京の人口って何人だっけ 」など、単純な疑問については検索エンジンを使えばほとんどの場合は解決するでしょう。
一方で、②の役割も欠かせません。
ネット上で人気のあるページには多くの人が集まるので、「 そこに広告を出したい 」と考える企業がいます。これは広告ビジネスの基本で、テレビや紙メディアでも同じです。
サイト運営者は広告収入を受け取り、広告主も多くの消費者に商品・サービスをチェックしてもらえるため、双方にとってWin-Winといえます。
SEOは「 検索エンジンに良い評価をしてもらう 」手法
SEOは「 Search Engine Optimization 」の略称で、ウェブサイトが検索エンジンの上位に表示されるための手法のことを指します。
Web検索において検索順位はとても重要で、例えば1位と5位であったとしてもクリック率に大きな差が生じます。
・1位:28.5%
・2位:15.7%
・3位:11.0%
・4位:8.0%
・5位:7.2%
数値出典:SISTRIX
これが10位以下ともなるとなかなかクリックされないので、ウェブ上で集客を図るのであれば検索順位はかなり重要です。
しかし、「 ウェブサイトを運営するなら、必ずSEO対策をしなければならない 」わけではありません。
集客や収益化を考えない、趣味でのサイト運営ならSEOは無視しても構いませんが、少しでもビジネス利用を図るのならSEOは必須でしょう。
検索エンジンはGoogle一択
検索エンジンにはGoogle・Yahoo・bingなどがありますが、使用率で圧倒的トップを誇るのはGoogleです。
日本国内だけでなく、世界規模で見てもGoogleのシェアはずば抜けています。
したがって、SEOを考えるときはGoogleを意識しておけば問題はありません。
「 普段はYahooを使っているんだけど…… 」という場合も、サイト運営をする上ではGoogle重視で考えるようにするのがおすすめです。
また、SEO戦略を考える際には以下のGoogleの基本姿勢・理念を知っておくと良いでしょう。
・ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。
・ひとつのことをとことん極めてうまくやるのが一番。
・遅いより速いほうがいい。
・ウェブ上の民主主義は機能する。
・情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。
・悪事を働かなくてもお金は稼げる。
・世の中にはまだまだ情報があふれている。
・情報のニーズはすべての国境を越える。
・スーツがなくても真剣に仕事はできる。
・「すばらしい」では足りない。
出典:Google公式サイト
例えば「 パソコンの前にいる時だけではない 」というのは、ウェブサイトのモバイル対応が大切であることを示唆していると解釈できます。
その他にも「 ユーザーに焦点を絞る = ユーザーファーストなサイトにする 」「 ひとつのことを極める = 専門性の高いサイトにする 」ですから、このGoogleの基本姿勢からは多くのことを学べるでしょう。
検索エンジンの基本的な仕組み

具体的に、検索エンジンにサイトが表示されるまでの流れは3つに分かれています。
①クローリング
まず最初に行われるのがクローリングで、これは「 巡回 」という意味です。
私たちが普段見ているウェブサイトは、作ってすぐに検索エンジン上に出現するというわけではありません。
私たちが見る前にGoogleのシステムがサイトデータをチェックしています。
「 ユーザーが検索する前から、ウェブクローラは膨大な数のウェブページから情報を収集し、検索インデックスに登録して整理しています。」
という一文がGoogleの公式サイトに記されており、クローリングは「 情報の収集 」という役割を持っていることがわかります。
何らかのサイトを作った場合、まずは検索エンジンにクロールしてもらわないことには何も始まりません。
そのため、「 クロールされやすいサイトを作る 」ことがまずSEOで優位に立つ第一歩ともいえます。
②インデクシング
クロールが終わるとインデクシングという段階に移ります。
インデクシングは「 収納・格納 」という意味で、クローリングによって得た膨大なデータをデータベースに登録していくフェーズに当たります。
このデータベースに収納されることで、私たちが作ったサイト・ページは検索エンジンに表示させることが可能となるのです。
言い換えると、インデックスに登録されなかったサイトは検索結果に表示されません。
後述する「 SEOペナルティ」の中にはインデックス削除という罰則もあり、かなり重い措置であると考えられます。
関連記事:SEO インデックス
③スコアリング
最後はスコアリングです。
実際の検索結果だと「 順位 」が存在することは先ほど述べた通りですが、この順位を決めているのがスコアリングです。
Googleが定めた評価基準に従い、インデックス登録されたサイト・ページの順位付けを行なっていきます。
「 評価基準さえわかればSEOで勝ち続けられる! 」とも考えがちですが、その基準をすべて特定するのは困難です。
しかしSEOのヒント自体は与えられています。
上述したGoogleの基本姿勢や「 ウェブマスターガイドライン 」を熟読することで、Googleがどういったコンテンツを私たちに求めているのかの予測は可能です。
ガイドラインURL:Google検索セントラル
SEO内部対策

続いて「 サイト運営で、具体的にどういったSEO対策をすればいいのか? 」について見ていきましょう。
SEO対策には、下記の2種類があります。まず内部対策から解説します。
・内部対策( サイトの内部に対して行なう )
・外部対策( サイトの外部に対して行なう )
タイトルにキーワードを含める
まず基本として、タイトルには狙ったキーワードを入れましょう。
ページタイトルはそのまま検索結果に表示されるので、検索してくる人に「 このサイトには求めている答えがありそうだ 」と感じてもらえるようなタイトルにするべきです。
タイトルの文字数は短すぎても長すぎてもNGで、30文字前後に収めるようにしてください。
メタディスクリプションを書いておく
メタディスクリプションは、検索結果でタイトルと併せて表示されるサイトの説明文です。
例えば、東京都公式サイトのメタディスクリプションは下記のようになっています。
「 東京都庁の公式ホームページ。都政に関する最新情報、記者会見、都議会や各局の情報、統計、入札・契約情報、知事への提言など。」
そのサイトの特徴は何なのか、どういった情報が入っているのか……などを、簡潔に説明するのがメタディスクリプションです。
設定していないサイトもありますが、ユーザビリティを高めるのであれば、ぜひ書いておきましょう。文字数としては100文字程度にするのがおすすめです。
関連記事:SEO meta
画像にalt属性を入れる
alt属性は「 代替テキスト 」のことで、webページで画像を使っていくのなら忘れずに設置しておきましょう。
alt属性を使うメリットは3つあります。
①画像が表示されなかったときの対策
何らかの問題が起こって画像が表示されなかったとき、代わりにalt属性のテキストが表示されます。
これによって、「 ここには◯○についての画像が入る予定だったんだな 」とユーザーに理解してもらうことができます。
関連記事:SEO alt属性
②SEO上のメリット
検索エンジンのクローリングシステムは、画像の内容を人間のように認識することができません。
そのため、「 これは紅茶に関する画像です 」と説明したいのであれば、代替テキストに「 紅茶 」などと記載しておく必要があります。
ページタイトルにキーワードを入れるのが当たり前であるように、画像にもキーワードを入れておくようにしましょう。
③視覚障がい者への配慮
視覚障がい者がウェブサイトを利用する際、音声読み上げ機能を使用します。
通常のテキストであれば問題なく読み上げてくれますが、画像だと音声で伝えるのは困難です。
代替テキストを用意しておけば、画像の内容についても説明が可能となります。
見出し構成を整える
webページの見出し( hタグ )にはh1〜h6の6種類があります。これらは適当に使うのではなく、ルールを守りましょう。
h1は「 1ページに1つ 」ですし、h3がh2よりも上にくることはありません。新たにページを作るときは「 h1 > h2 > …. > h6 」といった順序をしっかり意識して下さい。
ちなみに、全てのhタグを使わなくてもOKです。
「 h1とh2だけ 」「 h1からh3まで 」といった構成でも問題なく、各見出しごとに内容がまとまっていることの方が重要です。
サイトマップの作成
サイトマップはその名の通り「 ウェブサイトの地図 」ともいうべき存在です。
そのサイトがどういう構造になっているのか( =各ページがどう繋がっているのか )を示す役割を担い、ユーザビリティを高めます。
サイトマップはユーザー側だけでなく、検索エンジン側にとっても重要で、サイトマップを用意しておくことで、検索エンジンに全てのページを忘れずにチェックしてもらいやすくなります。
より細かくいうとサイトマップには以下の2種類があります。
- HTMLサイトマップ:ユーザーのため
- XMLサイトマップ:検索エンジンのため
両方作っておくのがベストで、WordPressを使っているなら以下のプラグインで簡単に作成が可能です。
- PS Auto Sitemap:HTMLサイトマップの作成
- XML-Sitemap:XMLサイトマップの作成
パンくずリストを用意
パンくずリストと聞くと「 何それ? 」と感じるかもしれませんが、実は目にしたことのある人も多いはずです。
これはサイトの現在位置がどの階層にあたるのかを示したリストで、例えば「 ホーム> カテゴリー > SEO 」もパンくずリストの1つです。
各項目をクリックorタッチすればその階層に飛ぶことができるので、ユーザーがサイトを移動しやすくする上で必須の要素といえます。
そんなパンくずリストの設定方法ですが、WordPressテーマによっては自動的に作成してくれるものもあり、大変便利です。
そうでない場合でも、「 Breadcrumb NVXT 」というプラグインを使うことで簡単に設定が可能です。
Breadcrumb NVXTプラグイン:Breadcrumb NavXT
ディレクトリ構造と内部リンクを整理
サイトマップとパンくずリストを用意すべき理由は、「 検索エンジンとユーザーがサイト構造を把握しやすくするため 」でした。
サイト構造という点でさらに重視して欲しいのが、ディレクトリ・内部リンクです。
ディレクトリ構造
サイト内の階層を示す構造のこと。
内容はサイトごとに異なりますが、例えば「 TOPページ > 記事カテゴリ > 各記事ページ 」というものが挙げられます。
内部リンク
自サイト内に貼られたリンクのこと。ユーザーが別記事・別コンテンツへ移動するのを助けます。
ディレクトリ構造が複雑になっているとクローラが巡回しにくく、SEOでは不利になります。
ディレクトリの階層数を増やしすぎた結果、「 空っぽの階層 」「 スカスカの階層 」が生まれてしまうのも良くありません。各階層に満遍なくコンテンツを入れるようにしましょう。
理想のウェブサイトは「 すべてのページに数クリックで辿り着けるサイト 」とされています。長くサイトを運営していると、コンテンツが増えすぎて全体の構造が複雑化してしまうこともあるでしょう。
そういった場合はディレクトリ構造・内部リンクを一度整理してすっきりとした形にするのをおすすめします。
関連記事:SEO 内部リンク
表示速度の改善
検索結果からサイトをクリックしたときに、なかなかページ内容が表示されずにイライラしたことはありませんか?
気長に待つこともあれば、仕方なく「 戻る 」を押したこともあるでしょう。
ユーザー全員が辛抱強いとは限らないので、ウェブサイトの表示速度はとても大切になってきます。
先ほど述べたGoogleの基本姿勢でも「 遅いより速い方がいい 」という項目があり、実際にGoogleもスピードアップデート( 表示速度をランキング要素に組み込む )を行なった経験があります。
自分が運営しているサイトがどの程度のスピードなのかを知るために、一度「 PageSpeed Insights 」などのツールで計測してみることをおすすめします。
PageSpeed Insights: PageSpeed Insights
もし表示速度が遅いと判定された場合、以下の解決策を試してみましょう。
・ページ内の画像サイズを小さくする
・CSS,Javascriptなどの外部ファイルを圧縮する
サイトをモバイル対応にする
昔のウェブサイトであればパソコン対応で充分だったかもしれませんが、今ではモバイル対応( スマートフォン対応 )は必須です。
スマートフォンが普及した今日では、モバイル対応をしないサイトはそれだけでSEO評価が落ちてしまいます。
ここでいうモバイル対応とは「 レスポンシブデザイン 」のことで、どのデバイスでアクセスしてもページのレイアウト・表示が崩れないようにする必要があります。
レスポンシブ対応がされていないサイトにスマートフォンで入った場合、文字や画像が小さすぎて読みにくく不便です。
パソコンとスマートフォンだけでなくタブレットを使用する人もいるので、この3サイズに対応できるような設定をしておきましょう。
SEO外部対策
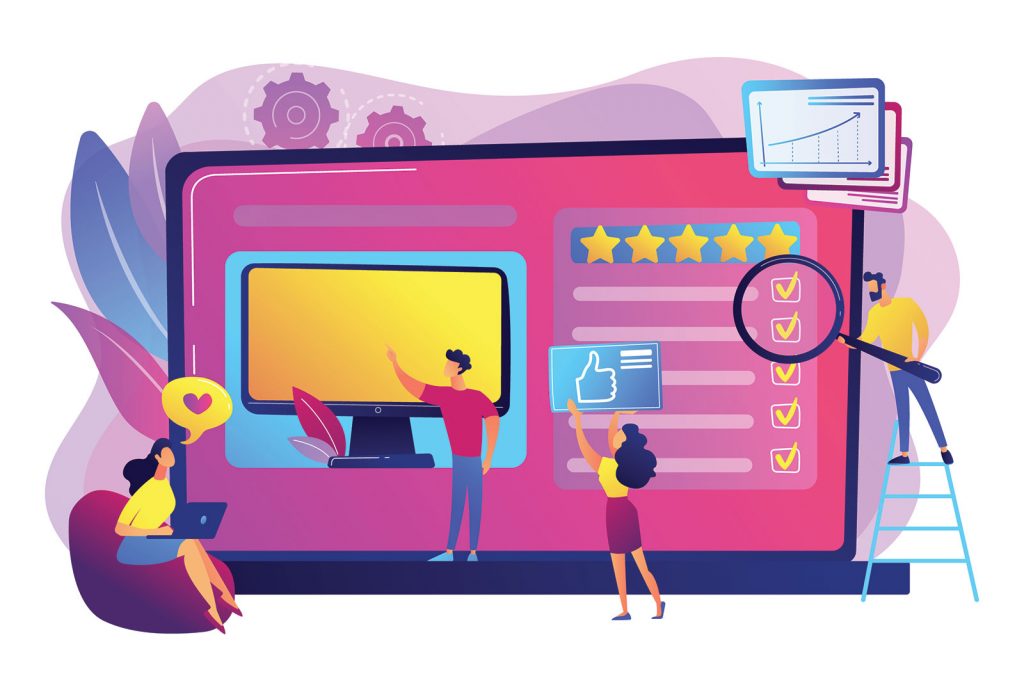
続いて、外部対策についてです。
これは「 サイトの外部に行なうSEO対策 」という意味になりますが、文字だけだと具体的に何なのか分かりにくいかもしれません。
関連記事:SEO 外部対策
外部対策は 「 被リンク 」で決まる
外部対策においてポイントとなるのが「 被リンク」です。
サイトが他のサイトやSNS上などでリンクされることが、「 被リンク 」にあたります。
被リンクという形で紹介されることは、そのサイトはユーザーにとって価値があるという何よりの証拠です。
関連記事:SEO 被リンク
被リンクの注意点
ここで1つ気をつけて欲しいのが、「 低品質な被リンクはむしろ逆効果である 」という点です。
もし被リンクの数だけで評価が上がるのであれば、「 いろいろなサイトにひたすらリンクを貼って貰えばOK 」ということになります。
被リンクの数を稼ぐために、ボリュームの薄いサイトを大量に作ってそこにリンクを掲載……なんてこともできてしまうでしょう。重要なのはあくまでも「 自然に生まれたリンク 」です。
つまり、外部対策でサイトの評価を上げるには、以下の2つが大切です。
- 質の高い外部リンクを増やす
- 悪い外部リンクは削除する
良質な外部リンクを獲得するには?
良質な外部リンクは「 関連性の高いサイトからの被リンク 」で生まれます。
なるべく多くの人に被リンクしてもらうためにぜひ活用したいのが、SNSです。
Twitter・FacebookなどのメジャーなSNSへすぐ連携できるようにしておけば、サイトを訪れた人が簡単にリンクを貼ることができます。
サイト更新したときにSNSで宣伝するのもおすすめです。
ちなみに、被リンクを簡単にチェックする際は、先ほど紹介したサーチコンソールが便利です。以下を分かりやすく把握することができます。
- 外部リンクの詳細
- 内部リンクの詳細
- リンク元サイト
- リンク元のテキスト
低品質な被リンクの削除・否認
もし悪い被リンクが多発した場合は、そのリンクを削除・否認するという選択肢も生まれてきます。
「 悪い被リンク 」の例として、以下のものが該当します。
- 同じドメインから大量のリンクが発生している( スパムリンクに近い )
- コンテンツのテーマからして関連性が見られない
- 過剰に多い相互リンク( 意図的にリンクを作っている )
被リンクを削除したい場合は、リンク先のサイト運営者に削除依頼を出しましょう。
とはいえ全ての運営者が返事をしてくれるとは限らないため、もし対策を打ってくれないのであれば最終手段として「 リンク否認ツール 」を使います。
しかし、この否認ツールはGoogle曰く「 複雑な機能 」であり、扱いに注意が必要です。
( 以下:リンク否認ツールのページから抜粋 )
使い方を間違えると、Google 検索結果でのサイトのパフォーマンスに影響が及ぶ可能性があります。
ご自身のサイトに対して、スパム行為のあるリンク、人為的リンク、品質が低いリンクが数多くあり、それが問題を引き起こしていると確信した場合にのみ、バックリンクを否認することをおすすめします。
参考:https://search.google.com/search-console/disavow-links
SEOでペナルティになることもある

検索順位を上げるためにSEO対策は積極的に行なっていくべきですが、Googleのガイドラインを逸脱した施策は逆にマイナス評価を受けることがあります。
これが「 SEOペナルティ 」です。
SEOペナルティを受けた結果、順位UPどころかウェブサイトがダメージを受けてしまうことも有り得るので、気をつけましょう。
以下、具体的に解説します。
関連記事:SEO ペナルティ
ガイドラインに違反するSEO対策とは?
ガイドラインとは、先ほど登場した「 ウェブマスターガイドライン 」のことです。
Googleがウェブコンテンツに求める要素・ポイントが記載されており、このガイドライン項目に従った運営をするのがベストとされています。
ガイドラインに逸脱するようなSEO手法として、以下のものが挙げられます。
- 隠しテキスト
- 隠しリンク
- キーワードの過剰な詰め込み
- 低品質なリンクを大量に設置している
- 低品質なコンテンツが大量に存在している
隠しテキストや隠しリンク( ユーザーの目につかないよう、こっそりSEOキーワード対策を施す )はある意味で「 ユーザーを騙す行為 」であり、こういった手法をGoogleは批判しています。
「 キーワードを大量に入れればSEOで有利になる 」というのも間違いで、ペナルティの対象になり得るだけでなく、ユーザーが読みにくいと感じる原因にもなるでしょう。
「 低品質なコンテンツ 」は定義が難しいですが、「 ユーザーに価値をほとんど提供していないコンテンツ 」であると考えて下さい。
内容が薄すぎるサイト、別のサイトからコピー&ペーストしただけのサイトは価値が低いと判定されます。
ペナルティの対象になるとどうなる?
ペナルティを受けると以下の2つが起こります。
- ページがインデックスから削除される
- 検索順位が下がる
検索順位ダウンに関しては、一気に下落するパターン・緩やかに加工していくパターンの両方があります。
ガイドラインを遵守したサイト運営をしていればペナルティの対象になる心配はまずありませんが、アクセス数・検索順位などの数値は日常的にチェックするようにしましょう。
ウェブ検索関連の統計は「 Googleサーチコンソール 」で確認するのがおすすめです。これ1つでクリック数・クリック率・平均順位をキーワードごとに確認できます。
公式サイト:Googleサーチコンソール
SEOの仕組みは変化していく

SEOのアルゴリズムシステムは頻繁に変化していくので、サイト運営側もその変化に順応していくことが求められます。
特に「 コア・アップデート 」と呼ばれる大規模なアルゴリズム変動は、検索順位にしばしば大きな影響を与えます。
それまで上位表示されていたサイトが下位に沈むという例も珍しくありません。
ネットビジネスで有名なのがアフィリエイトですが、「 アフィリエイトは安定しない 」と言われる理由がこのアップデートにあります。
苦労してサイト更新を重ねたとしても、アルゴリズム変動で順位が伸び悩んだりすることもあるためです。
検索エンジンの環境がどう動いていくかはGoogleにしかわからないので、こちらが予想しても意味はありません。
以下の2点を意識し、サイト運営をしていくことをおすすめします。
- ユーザーにとって使いやすいサイトを作る
- 検索を行なうユーザーに対し価値を提供できるようなサイトにする
おわりに

SEO・検索エンジンの仕組みは一見、複雑そうに見えますが「 クローリング→インデクシング→スコアリング 」の3つを押さえておけばひとまずはOKです。
SEOを意識したサイト運営をしていく場合、ぜひ考えて欲しいのが「 Googleはどういったコンテンツを求めているか? 」という点です。
趣味の範囲でサイトを作るのなら別ですが、収益化・ビジネス目的であればGoogleの基本姿勢はぜひ、チェックしておきましょう。
検索エンジンを取り巻く環境がいかに変化したとしても、Googleが理想とするコンテンツを提供し続けていくようにすれば、そのサイトは自然と評価されやすくなります。
小手先のSEOテクニックだけに頼るのではなく、「 価値のあるサイトを作る 」を意識してサイト運営を行なっていきましょう。
