WEBに関する知識詳がなくても、「 SEO 」という言葉自体は、皆さんどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。SEO( SEO対策 )は、「 Search Engine Optimization 」 の略で、「 検索エンジン最適化 」を意味します。
つまり、インターネット検索結果で自社のWebサイトを上位表示させたり、検索結果画面により多く露出するための一連の取り組みのことを「 SEO( SEO対策 )」と私たちは呼んでいます。
では、SEOに取り組む最終的な目的は何でしょうか?
それは、SEOに取り組むことでWebサイトへの検索流入やコンバージョンの増加に繋げ、売上の向上に繋げるためです。すなわち、SEO対策をすることで結果的に企業成長まで見込めるようになるということです!
そのような素晴らしい結果を出すには、まずSEOの基礎知識やGoogleの検索エンジンについての理解を深めることが大切です。
そこで今回は、SEO初心者の方にも分りやすい内容で、重要なポイントに絞ってまとめました。本記事を参考にして、上位表示されるような質の高いコンテンツを配信できるよう頑張りましょう!
1.SEOとは?

冒頭でも説明しましたが、SEO( SEO対策 )とは「 Search Engine Optimization 」の略で、「 検索エンジン最適化 」のことです。
これは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンに向けてWebサイトが評価されるようにすることを意味します。
つまり、インターネット検索結果でWebサイトを上位表示させ、多くのユーザーの目に触れるようにする取り組みのことを「 SEO( SEO対策 )」と呼びます。
ちなみに、SEOの読み方は「 エスイーオー 」です。SEOという時もあれば、SEO対策という時もありますが、その言葉の意味の違いは特にありません。
オーガニック検索からの流入は、自ら何かを探して特定のキーワードで検索してたどり着くユーザーが多いため、コンバージョン( 成約 )に繋がりやすい傾向にあります。
SEOに成功する → 安定してモチベーションの高いユーザーのサイト流入が見込める
そして、最終的に売上向上から企業成長まで見込めるようになるのがSEOです。
1-1 SEOの目的は何?
まず初めに覚えておいていただきたいのが、「 SEOの目的はWebサイトを検索上位に表示させることだけではない 」 ということです。
実際に、上位表示させることはWeb集客のための入り口作りに過ぎません。
SEO対策の内容ばかりに囚われて本来の目的を見失ってしまいがちですが、最終的にWebサイトでコンバージョン( 成約 )の達成に繋がって初めてSEOの意味があります。
SEOの本当の目的は、Webサイトを検索上位に表示させるのではなく、成約に繋げるためだというくらいに考えておくと方向性を間違うことはないでしょう。
では次に、SEO対策をすることで得られるメリットについて簡単に紹介します。
1-2 SEOのメリット4つ
* 広告とは違い無料で施策を打つことができる
* 検索結果で上位に表示されることで安定した集客が見込める
* オーガニック検索からの流入ユーザーはモチベーションが高く成約に結びつきやすくなる
* 企業名や商品名が上位表示されることで、ブランディング強化に繋がる
では次に、デメリットを見てみましょう。
1-3 SEOのデメリット4つ
* SEOを実施してから4ヶ月から1年ほど効果が出るまで時間がかかる
* コンテンツ作成などに対して人的コストがかかる
* キーワードによっては競合が多く上位表示が難しいケースがある
*ノウハウがないと効果が見込めず失敗に終わる場合がある
SEOに成功するメリットはたくさんありますが、効果を出すまでに時間や人的コストがかかることが分かります。
また、ノウハウがなければ間違った方法でSEO対策をしてしまうことになり、せっかくの時間とお金が無駄になってしまいかねませんので、ここから本記事をしっかりと読み込んでくださいね!
2.SEO対策で大切なポイントは?

それではここから具体的な対策方法について解説していくことになりますが、 SEOを行う上で最も重要なのは
・ユーザーに対して価値のある情報の提供( 問題解決に繋がる、新しい情報を得られる等 )
・検索エンジンに正しく内容を伝える( 検索エンジンが認識しやすい文章・記述にする等 )
ということです。
ユーザーが長く滞在したくなるような充実したコンテンツでなければ、機械的にSEO対策を行っても上位表示は見込めません。
また、ユーザーにとっては価値があっても、検索エンジンが認識できないコンテンツだと上位表示することができず、そもそもユーザーに見てもらうことすら叶いません。
そのため、ユーザーに対して価値のある情報を盛り込むことは当たり前で、それを検索エンジンに正しく評価してもらえるWebサイトにするために対策する!と考えていただけると、初心者の方でも難しく考えずにSEOに取り組めると思います。
関連記事:SEO 対策の方法・費用・効果を徹底解説
2-1 SEOには「 内部対策 」と「 外部対策 」がある
では、「 価値のあるWebサイトですよ!」ということを検索エンジンに伝えるにはどうすればいいのでしょうか。
まず初めに、SEOの具体的な施策は「 内部対策 」と「 外部対策 」に分けられます。
◆内部対策とは
内部対策とは、自社Webページのコンテンツを改善することを言います。内部対策には、見出しタグ、画像タグ、内部リンク構造、インバウンドリンク(バックリンク)など、様々な要素があり、それぞれ対策することで検索エンジンにテーマ性を正しく評価してもらうことができ、上位表示に繋がります。
◆外部対策とは
外部対策とは、Webサイトの外部要因を改善することでSEO効果を高めることを言います。
具体的には、他のWebサイトに掲載されている被リンク( 自分のWebサイトのリンク )の数を増やすことが外部対策にあたります。これは、「 他のWebサイトにリンクが貼られている = 紹介する価値があるサイト 」と考えられるため、検索結果の順位を決める基準の1つとされています。
「 外部対策 」は自分ではコントロールしづらい部分ですので、SEOでは基本的に「 内部対策 」が重要とされています。
関連記事:SEO外部対策の重要性【上位表示に必要なポイント】
3.まずはGoogleの考え方を身につけよう!

検索結果では、Googleが考える「 ユーザーにとって価値のあるページ 」が常に上位に表示されています。
そして、それらのページより上に表示させるということは、自分のWebサイトのページをそれ以上に価値があり、独自性が高く、高品質で網羅的なコンテンツにしていく必要があるということです。
また、SEOは基本的にGoogleの検索エンジンに対して行うものなので、「 SEO対策 = Google対策 」と考えましょう。
それでは、「 なぜGoogleの考え方に沿うことで上位表示できるのか 」という理由から見ていきましょう!
3-1 日本における検索エンジンのシェア
SEO対策を「 Google対策 」と考える理由は、Googleは日本だけで見ても75%以上のユーザーが利用しており、シェア率約20%のYahoo!もGoogleの検索アルゴリズムを利用しているため、検索エンジンは事実上Googleの寡占状態と言えるからです。
| 検索エンジン | Yahoo! | bing | その他 | |
| シェア率 | 75.43% | 19.57% | 4.45% | 0.54% |
すなわち、Googleの検索エンジンを対象にSEOに取り組み、検索結果で上位表示したりと露出を増やすことができれば、効率的にWebサイトのアクセス数を増やすことができるということになります。
3-2 Googleが重要視する3つの評価基準「 E-A-T 」
Googleの検索品質評価ガイドラインでは「 E-A-T 」の重要性が述べられており、Webサイトやそのコンテンツを作成する際に、この3つの要素をしっかり取り入れることが評価に繋がります。
Googleが最重要視する3つの評価基準( E-A-T )
| * Expertise( 専門性 )
* Authoritativeness( 権威性 ) * Trustworthiness( 信頼性 ) ※Googleの検索品質評価ガイドラインより |
次に、これら3つの要素を分かりやすく説明します。
3-2-1.Expertise( 専門性 )とは?
コンテンツ内容やWebサイト全体が、何かの専門性に特化しているかどうかという観点です。ありとあらゆる内容を含む雑記的なWebサイトより、一つの内容に特化したWebサイトのほうが高く評価されるということです。
そのため、その分野に精通した人が記事をアップしていくようなWebサイトだと、評価が効果的に高まる可能性もあります。
3-2-2.Authoritativeness( 権威性 )とは?
誰が見ても「 このコンテンツの内容は正しい情報だ! 」と思えるかという観点です。
特定の分野で素人が運用しているようなWebサイトよりも、その分野において一定の地位を獲得していることが重要です。「 知名度 」や「 ブランド力 」とも言い換えられます。
また、権威性に関してはコンテンツの内容だけでどうにかできるものではなく、長期間Webサイトを運営しているという実績にも関連します。長い期間をかけて、じっくりWebサイトを育てましょう。
3-2-3.Trustworthiness( 信頼性 )とは?
多くの人から信頼されているかWebサイトかという観点です。匿名で投稿されているようなコンテンツよりも、企業名がしっかり載っていて、更にそのコンテンツは誰が作成したのかなども記載されていることが高ポイントに繋がります。
Webサイトの運営者情報やプロフィールを充実させ、見る人の不信感を無くすことが大切です。
これら3つの要素が大きく欠如している場合は、「 質の低いWebサイト 」と判断される可能性があります。いわゆる指針のようなものですので、コンテンツ作成を始める前の段階から注意しておく必要のある内容です!
3-2 Googleが掲げる10の事実
Googleは、「 Googleが掲げる10の事実 」として会社の理念を掲げています。
Google は、これらが事実であることを願い、常にこのとおりであるよう努めています。そのため、これらの理念はGoogle検索エンジンの判断基準にも自然と関連してきます。
しっかりとGoogleの考えを理解し、自分もGoogleの一員になったような感覚でWebサイトやコンテンツ制作を進めることが、SEOを成功させるカギとなるかもしれません。
Googleが掲げる10の事実
| 1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。
2. 1 つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。 3. 遅いより速いほうがいい。 4. ウェブ上の民主主義は機能します。 5. 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。 6. 悪事を働かなくてもお金は稼げる。 7. 世の中にはまだまだ情報があふれている。 8. 情報のニーズはすべての国境を越える。 9. スーツがなくても真剣に仕事はできる。 10. 「すばらしい」では足りない。 ※Googleについて/10の事実 より |
すなわち、我々が理解しておくべきこととして言い換えるならば、
・コンテンツはユーザー目線で作成することを第一に考える!
・専門性や独自性を高め、網羅することが質の良さである!
・ユーザーのためにページの表示スピードも考慮する!
・ページの人気度( 被リンクの数 )は評価に繋がる!
・どんな時にどんな人がどんな情報を必要とするかを考える!
というような感じになります。
これらの内容をしっかり押さえ、ユーザーの検索ニーズを満たす高品質で価値のあるコンテンツを作成し、多くの人から信頼され紹介してもらえるページに育てていきましょう。
そうすることで、自然とGoogle検索エンジンからの評価は上がり、検索上位に表示されるようになるでしょう。
4. SEOで順位が決まる仕組みって?

それでは、検索結果のランキングはどのように決定されるのでしょうか?
その答えを知るには、まず「 検索エンジンの仕組み 」を理解する必要があります。
ここで、SEOで順位が決まる仕組みについて確認していきましょう!
4-1 「 クロール 」と「 インデックス 」
まず、SEO対策をどんなに行なったとしても、その対策した結果を検索エンジンに認識してもらえなければその効果は出ないと覚えておいてください。
検索エンジンにページが認識されるためには、Google検索エンジンに「 発見 」され、Google検索エンジンのデータベースに「 登録 」される必要があります。
ちなみに検索エンジンが「 発見 」することを「 クロール 」と言い、クロールを行うロボットのことを「 クローラー 」と呼びます。そして、検索エンジンがページをデータベースへ「 登録 」することを「 インデックス 」と呼びます。
しかし言葉だけでは少しイメージしにくいので、クロールとインデックスの関係は、よく「 図書館 」に置き換えて説明されます。
| 検索エンジン | 図書館 |
| ① クロールによってページを集める | ① 本の内容を確認する |
| ② ページをインデックスする | ② 本をジャンルごとに本棚に入れる |
いかがでしょうか?図書館に例えることで、クロールとインデックスの関係が分りやすくなったかと思います。
それでは次に、Googleはインデックスをした後に、どのようにランキングをつけているのかという仕組みについて解説します。
関連記事:【解説】SEO対策でインデックスを効果的に使用する方法
4-2 検索アルゴリズムとランキングの仕組み
検索エンジンは、ユーザーに適したコンテンツを検索結果に出すよう動いています。一体どのような仕組みになっているのでしょうか。
私たちが何かを検索する時、検索エンジンは関連性の高いコンテンツをデータベースから抽出し、検索した人の期待に応える情報が詰まっているだろうコンテンツを上から順に表示します。
これがコンテンツのランキングの仕組みであり、ランキングを付ける仕組みのことを「 検索アルゴリズム 」と呼びます。
そして検索アルゴリズムは、対象となるページに対し、検索キーワードに応じて得点付け( スコアリング )するためのものです。
年々アルゴリズムの精度が上がってきており、検索したユーザーにとってより関連度が高く、有益な情報を検索結果に表示できるようになってきました。
すなわち、
検索結果ランキング1位 = 検索したユーザーが知りたい情報が1番詰まっている
ということが言えてしまう時代になっているということです。
今後もアルゴリズムが進化すればするほど、SEO対策をして自社のページを上位表示させることは、ますます重要になると言っても過言ではないでしょう。
5.SEO対策前に準備するツールはこれ!
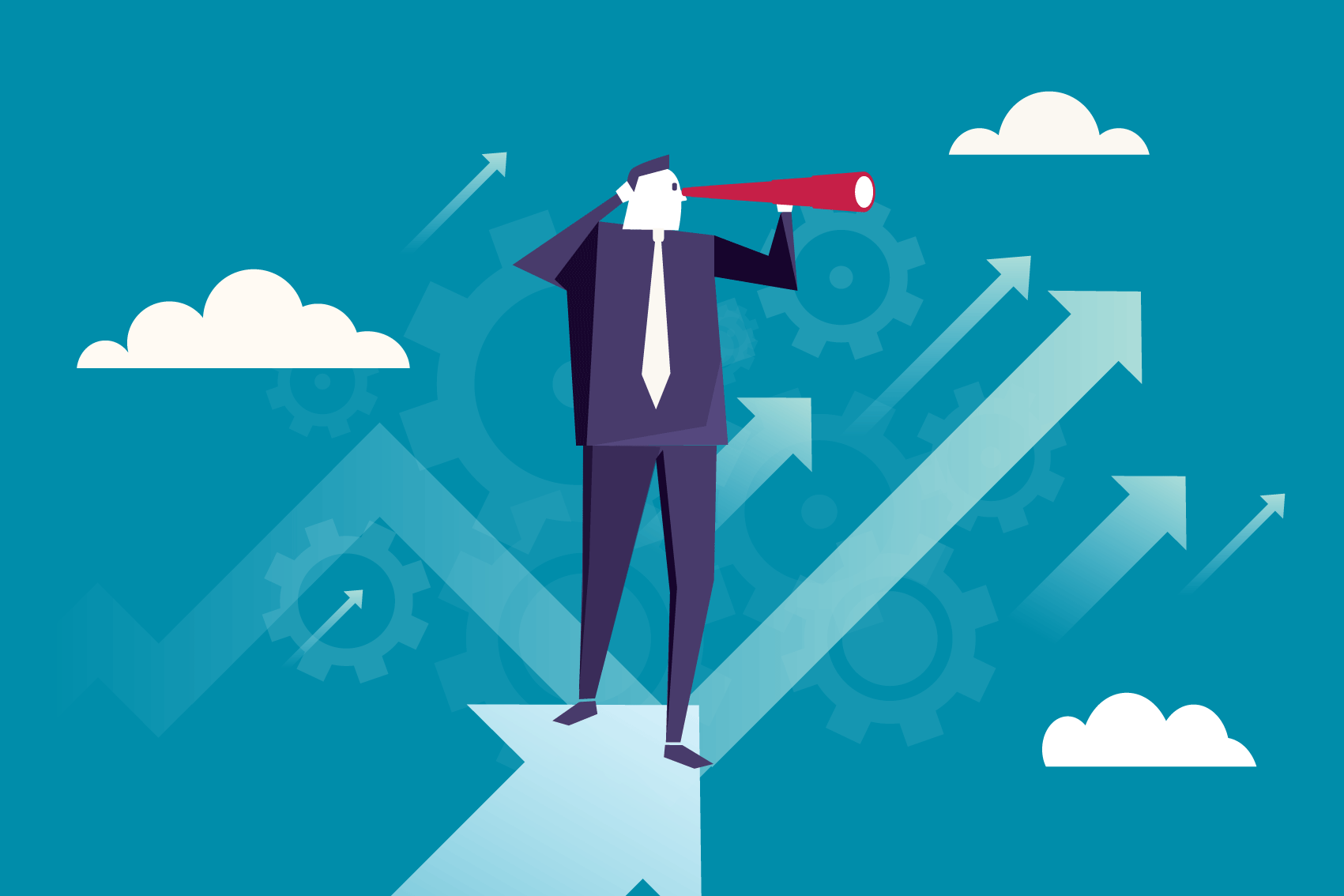
SEOに本格的に取り掛かる前に、サイトの成長を管理していく上で欠かせないツールがあります。
それは、「 Google Search Console 」と、検索順位をモニタリングするための「 検索順位チェックツール 」と呼ばれるものです。
5-1 Google Search Console( Googleサーチコンソール )
Googleサーチコンソールとは、Googleが無料提供する高機能サイト解析サービスのことです。これを利用すると検索での見え方、検索トラフィック( どんなキーワードで検索してサイトにたどり着いたか )、クロール( 検索エンジンに見つけてもらえているか )、Googleインデックス( 検索エンジンに登録されているかどうか )、セキュリティ、スパムなどあらゆる視点からサイトを管理することができます。
サイトが今どのような状況にあるのかを常にチェックすることができるので、SEOに取り組む際には必ず登録しましょう。
5-2 検索順位チェックツール
SEOを行う際、検索順位をチェックするのは必要不可欠な作業です。そして、検索順位をチェックするにはツールを利用すると非常に便利です。自身が公開したページの検索順位が、対策するキーワードで何位に位置するのかを把握しておきましょう。
ただ闇雲にSEOへ取り組むのではなく、順位を確認して改善を繰り返すことが上位表示の必須条件となります。
また、「 検索順位チェックツール 」に関しては様々なサービスがありますので、検索してみて自分の使いやすそうなものを選ぶと良いでしょう。
6.SEO対策を始める前に決めること!

SEOについての基礎知識や必要なツールについて理解できたところで、SEOを始める前の一番重要な作業となる「 検索キーワード 」について詳しく知っておきましょう。
検索キーワードとは、そのページに最も関連する語句やフレーズを意味します。簡単に言うと、「 ユーザーがどのようなキーワードで検索した時に、自分たちのページを表示したいか 」ということを考えて設定するワードのことです。
検索キーワードを選定する際は、ただ自分のイメージで何となく決めてしまうのではなく、下記のような点を考慮しなければなりません。
・ニーズのあるワードであるのか?
・ユーザーの検索状況などを踏まえられているか?
・コンテンツとマッチしたキーワードであるのか?
・1つのページに対し複数のキーワードに対応しようとしていないか?
ここからは、もう少し詳しく検索キーワードの選定方法を解説していきます。
6-1 検索キーワードを調査して選定する
まずは候補となるキーワードをできるだけ多く書き出してみましょう。また、候補となるキーワードがなかなか思い浮かばない場合は、検索エンジンのサジェスト機能 ( 検索キーワードを入力した際に、関連したワードを推測して表示してくれる機能のこと )を利用してみると良いでしょう。
関連記事:【SEO対策】キーワード選定の方法と便利ツール7選
6-2 キーワードの検索ボリュームを調べる
候補となるキーワードが出揃ったら、次はGoogleが提供している「 キーワードプランナー 」を利用してそれらのキーワードがどのくらい検索されているかという、検索ボリュームの確認を行います。
ここで注意していただきたいのが、決して検索ニーズの高いキーワードを選べば良いという話ではありません。何故ならば検索ニーズの高いキーワードであると、競合サイトが多く、上位表示が困難なケースが多いからです。
そのため、 あまり競合のいない、検索ボリュームがほどほどなキーワードが狙い目だと言えます。また、キーワードを細分化( 2種類以上を掛け合わせる )することで、上位表示が狙えます。
関連記事:SEO キーワード検索
6-3 キーワードの検索クエリタイプについて理解する
「 検索クエリ 」とは、Googleなどの検索窓にユーザーが実際に入力する単語やフレーズのことを指します。運営側がキーワードと呼ぶのに対し、ユーザー側はクエリと呼びます。
もう少し分かりやすく説明すると、Webサイト運営側は「 キーワード 」を設定してサイトやコンテンツを公開し、ユーザーは「 クエリ 」で欲しい情報を検索するというイメージです。
近年、Googleの検索アルゴリズムが進化するにつれて、ユーザーの検索意図とコンテンツの関係がますます重要視されるようになりました。
そこで運営側は、ユーザーがどのようなことを考えて検索しているのかという、3つの「 検索クエリタイプ 」について知っておくことが重要になります。
◆特定のサイトを検索する「 ナビゲーショナルクエリ( 案内型 )」
「 ナビゲーショナルクエリ 」は案内型クエリとも言われ、「 楽天 」「 Instagram ログイン 」という語句のように、ユーザーが特定のブランドやウェブサイトを見つけるために利用するキーワードです。
◆アクションを目的とした「 トランザクショナルクエリ( 取引型 )」
「 トランザクショナルクエリ 」は取引型クエリという意味もあり、「 子供 英会話 格安 」「 ヨガ教室 早朝 」など、ユーザーが予約や商品購入などのするために利用するキーワードです。また、これらは 直接コンバージョンに繋がりやすいキーワード群と言えます。
◆知りたいことがある「 インフォメーショナルクエリ( 情報型 )」
「 インフォメーショナルクエリ 」は情報型クエリとも呼ばれ、「 パスタ レシピ 」「 映画 ランキング 」などのように、ユーザーが何らかの問題に対して、知識や方法などに関する情報を集めるために利用するキーワードです。
と、以上の3つになります。少しはイメージできましたでしょうか。
それではこれら3つのクエリタイプを理解した上で、
・自分が選定したキーワードはどのクエリタイプに当てはまるのか
・検索上位にはどのクエリタイプのページが多いのか
をチェックし、 Googleがそのキーワードに対して評価しているクエリタイプに沿ったページコンテンツを作成するようにしましょう。
7. SEO対策①:Googleからサイトが適切に認識・評価されるようにしよう!

Googleから高評価を得ることができる高品質なコンテンツを作成するには、先ほど説明した「 E-A-T 」を考慮しましょう。
「 E-A-T 」は「 専門性・権威性・信頼性 」を意味しますが、実際に対策するために噛み砕くと、「 コンテンツの専門性・コンテンツの評判・コンテンツの質 」と言い換えることができます。これらについて対策することは、SEOを進めるにあたりとても重要になります。
それではここから、一つずつ見ていきましょう!
7-1 コンテンツの品質と量の関係性
まず、コンテンツ量( 文字数 )は多い方が上位表示に有利という分析結果があります。
すなわち それは、テーマに専門性を持たせたコンテンツは関連トピックを網羅しており、その結果コンテンツ量が多くなっている傾向にあるためです。
競合が少ないキーワードであれば1,000文字程度で上位表示される場合もありますが、難易度の高いキーワードであれば、2,000文字〜4,000文字程度で作成し、ユーザーに有益となる情報を分かりやすく届ける必要があります。
関連記事:コンテンツSEOとは?基礎知識から作業手順まで徹底解説
| <対策方法まとめ>
* そのキーワードで検索するユーザーに必要と思われるトピックスを網羅し、コンテンツ量を充実させよう! |
7-2 ページタイトルを最適化する
キーワードを選んだら、そのキーワードをページタイトル( <title>タグ )に盛り込むことは必須です。ページタイトルはSEOにおいて最重要ポイントになります。
キーワードを必ず含め、30文字程度で簡潔にまとめましょう。
また、ユーザーが欲しいのは、「 そのコンテンツを読むと何が得られるのか 」というベネフィットの情報です。クリック率を上げるためにも、キーワードだけでなく、ユーザーの心を掴むメッセージを端的に伝えましょう。
また注意点としては、スマートフォンで見た場合、検索結果に表示される文字数が20文字ほどに省略されてしまうことがあります。
そうしたことからも、重要なワードや伝えたいポイントはできるだけ前方に配置し、省略されても内容が理解できるように工夫しましょう。
| <対策方法まとめ>
* ページタイトルにはキーワードを含めた30文字程度に設定し、重要なワードはできるだけ前方に配置しよう! * 上位表示されている競合サイトのページタイトルと見比べ、同じページに並んだとしてもクリックしたくなるタイトルを考えよう! |
7-3 「 h1タグ 」は1つだけにし、順番通りに使う
h1タグとは、そのページにおいて最上位の見出しを記述するHTMLタグのことです。ちなみに、h1の ”h” は「 heading 」の略で「 見出し 」であることを表しており、h1〜h6まで6段階のタグがあります。
例えば本記事だと、以下のようなhタグ構成になっています。
・【h1】【完全版】SEOとは?基礎知識から対策方法まで分りやすく解説
・ 【h2】SEOとは?
・ 【h3】SEOの目的は何?
・ 【h3】SEOのメリット4つ
・ 【h3】SEOのデメリット4つ
・ 【h2】SEO対策で大切なポイントは?
・ 【h3】SEOには「 内部対策 」と「 外部対策 」がある …etc
h1はhタグの中で最上位の見出しであることを意味することから、タイトル( <title>タグ )に次いで重要な情報となります。h1にもキーワードをしっかりと含め、h1はページに対して1つだけ入れるようにしましょう。
また、その他のh2~h6のタグも同様に、できるだけキーワードやそれに関連するワードを含めることで、Webサイトのテーマ性の統一に役立ち、質の良いコンテンツとして評価されます。
hxタグはフォントサイズの変更のためなどには利用せず、正しい順番で使うことも評価基準に関わりますので注意しましょう。
| <対策方法まとめ>
・h1タグは1つのみで、必ずキーワードを含めよう! ・その他のhxタグも出来るだけキーワードや関連ワードを含めよう! ・文書構造を正しく表すために、必ずh1、h2、h3…と順番に使おう! |
7-4 meta description( メタ ディスクリプション )を設定する
meta description( メタ ディスクリプション )とは、Webページの説明文を検索結果に表示させる為に設定するmetaタグのことです。パソコンでの検索結果であれば120文字程度、スマートフォンで見た場合は50文字程度が表示されます。
meta descriptionには、検索したユーザーにそのページの内容について端的に伝える役割があるほか、Googleがページ内容を判断する基準にもなります。
ページタイトルと同様、キーワードやそのページから得られるベネフィットについても記述し、スマートフォンで見たときにもそれらがしっかり表示されるよう、重要な内容は出来るだけ前方に配置しましょう。
| <対策方法まとめ>
・meta descriptionにもページタイトルと同様、キーワードとベネフィットを入れよう! ・ページの内容を80〜100文字程度で簡潔にまとめ、重要なポイントは前方に配置しよう! |
7-5 キーワードバランスを考える
SEOにおけるキーワード出現数は、昔に比べて重要度は低くなってきていますが、キーワードをバランスよく配置することは大切です。
というのも、複数のワードを組み合わせたキーワードの場合、検索時の順位表示にキーワード出現比率の影響が出やすい傾向にあるからです。
また、キーワードの比率を自然な形に調整するのとあわせて、同じ単語の繰り返しは極力減らし、類似語で補いましょう。
その他にも、キーワードの関連語句などを文章中に利用することで、テーマ性を強めることができます。
| <対策方法まとめ>
・上位サイトとの差をチェックし、キーワードの比率を適度なバランスに調整しよう! ・同じ単語の繰り返しは極力減らし、類義語や関連語句を利用しよう! |
7-6 低品質サイトからのリンクを否認する
以前は、被リンク数( 外部サイトで紹介されている数 )が順位アップにつながる要因でしたが、現在は被リンクの質( サイトとの関連性 )が評価指標となってきています。
もちろん、 評価の高いドメインや関連性のあるページから被リンクを獲得することは、SEO対策として今でも重要なポイントです。
しかし、低品質なサイトからの被リンクが多い場合は、評価のマイナス要因となり、順位に影響を及ぼしてしまう可能性があります。
そこで、外部被リンクを調査してみることをおすすめします。
Google Search Consoleの「 検索トラフィック > サイトへのリンク 」から「 自サイト内のページにリンクしているドメイン 」、「 他のドメインからリンクされているページ 」で確認することができます。
もしそこで関連性のないリンクや不審なリンクを見つけた場合は、「 バックリンクの否認 」を行いましょう。
この操作をすることで、Googleがサイトを評価する際に、特定のリンクを評価範囲から外してもらえます。
| <対策方法まとめ>
・Googleサーチコンソールを使って被リンクを確認しよう! ・低品質なサイトやページからのリンクがあれば否認し、Googleの評価範囲から排除しよう! |
7-7 低品質なコンテンツをサイトから無くす
低品質コンテンツとは、情報量が少なくそれほど重要ではないページ、またはユーザーに対して検索結果に表示させる必要のないページのことを指します。
低品質なブログ記事などは削除またはリライトするべきですが、サイトの中には、申し込みフォームや、サイトマップ、誘導ページなどコンテンツとして省くことのできない情報量が少ないページも存在します。
そこで、 低品質コンテンツに該当するかも?と思われるページには「 noindex処理 」をして、インデックス( 登録対象 )から外し、サイト全体のページの評価を下げないようにしましょう。
方法としては、以下の要素をheadタグ内に記述することで可能です。
| <meta name=”robots” content=”noindex”> |
また、noindexの記述をしたページは、再度クロールされることで検索エンジンに認識されますのでご注意ください。
| <対策方法まとめ>
・低品質なページは削除またはリライトしよう! ・省くことのできない低品質なページは、検索エンジンのインデックスから除外し、サイト全体の評価を上げよう! |
8. SEO対策②:ユーザービリティを考慮したコンテンツにしよう!

ユーザビリティを考慮するということは、ユーザーにとって「 使いやすい 」、「 読みやすい 」ことを考えるということです。
UX( ユーザー・エクスピリエンス / ユーザー体験 )が高まれば、直帰率が下がるだけでなく、ユーザー1人1人の滞在時間も長くなることも見込めますので、サイト全体のパフォーマンス評価もぐんと上がります。
ここからは、結果的にSEOに繋がる「 ユーザーが使いやすいコンテンツ 」の作成方法を解説します!
8-1 ページからリンク切れURLを無くす
リンクが貼ってあるからクリックしたのに、リンク先のページが見つからなかった・・・なんて経験、皆さんも少なくないと思います。
もし公開しているページ内でリンク切れしているものがあれば、そのリンク先のURLを修正する、またはリンク先が閉鎖しているのであれば、そのリンク自体を削除するようにし、ユーザーがリンクをクリックした時の機会損失を減らすよう心がけましょう。
ちなみに、リンク切れはツールを使うことで簡単に検出することができますので、一度インターネットでツールについて調べてみるのも良いでしょう。
| <対策方法まとめ>
・リンク切れがあれば、修正または削除しよう! |
8-2 URLは簡素なものにする
自分で各コンテンツのURL名を設定できることがほとんどです。コンテンツ内容のテーマやタイトル名を参考にして、簡潔なURL名を設定することをおすすめします。
例えば、コンテンツのタイトルが「 SEOについて学ぼう!第1弾 」なのであれば、URL名は「 …./seo-1/ 」に設定するなどです。
こうしたURL名にすると、コンテンツの内容が想像しやすく、ユーザーから参照されやすくなるためSEO効果が期待できます。
反対にURL名が長いとユーザーの利便性は低下する傾向にあるため、気をつけましょう。
| <対策方法まとめ>
・URL名は簡素に設定し、コンテンツ内容をユーザーに分りやすく伝えよう! |
8-3 ページスピードを速める
「 Googleが掲げる10の事実 」のところでも置き換えて説明しましたが、Googleはページの読み込み・表示速度は速い方が良いと考えていることが分かります。
ただし、ページスピードが直接評価に関係する訳ではありません。
というのも、表示が速いページはUX( ユーザー・エクスピリエンス / ユーザー体験 )が向上する、すなわちユーザーにとって快適に見ることができるので、離脱率の低下やコンバージョン率の向上に繋がるなど、多くのメリットがあります。
特にスマートフォンを利用している時に、見たいと思ってそのサイトをクリックしたけど、表示が遅く待つのにイライラしてしまって開くのをやめた、なんて経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
Googleが提供している「 PageSpeed Insights 」を利用すると、サイトのページスピードのチェックだけでなく、モバイルフレンドリー( モバイル端末で使いやすいかどうか )も調べることができます。
ページスピードを速くし、スマートフォンからも快適に見られるページにすることはSEOで成果を上げることに大きく貢献しますので、必ず対策するようにしましょう。
| <対策方法まとめ>
・「 PageSpeed Insights 」を使ってページスピードとモバイルフレンドリーをチェックする! ・遅い判定が出た場合は、サイト内にある画像や参照ファイルを圧縮ツールなどを利用して軽量化する! |
8-4 ウェブサイトをスマホ対応にする
スマホ対応するには、「 レスポンシブデザイン 」という設計でサイト構築するのが簡単です。レスポンシブデザインを利用すると、PC向け、スマホ向け、とそれぞれページを作成しなくても、自動で最適なサイズで表示されるようになります。
現在はモバイルファーストインデックス、すなわちモバイルサイトを基準に検索順位が決定される時代になりました。
そのため、PCだけに限らずモバイル端末でもユーザーがストレスなくサイトを閲覧できる「 モバイルフレンドリー 」なウェブサイトを作ることができれば、SEOの評価ポイントに繋がります。
| <対策方法まとめ>
・レスポンシブデザインでスマホ対応にして、どのデバイスで見ても高いクオリティで表示されるようにしよう! |
8-5 読みやすいコンテンツを作る
「 読みやすいコンテンツ 」とは、そのデザインや文脈を考慮することで成り立ちます。例えば、下記のような工夫です。
・誤字・脱字をなくす
・ファーストビューや文中に関連性のある画像を挿入する
・トピックを分けたり、行間を適度に空けたりする
・重要なところは太字や赤字にしたり、下線を引くなどして文章を強調する
・文章はなるべく区切り、分りやすくテンポよく読める内容にする
文字のサイズなどもそうですが、自分の作成しているコンテンツに関連があり、読みやすいと感じるページを見つけたら、そのページにある文章の構成や装飾などを参考にしてみると良いでしょう。
| <対策方法まとめ>
・画像を挿入したり、文字を装飾したりして、ユーザーの読みやすいコンテンツにしよう! |
8-6 挿入画像の代替テキスト( alt属性 )を記述する
まず、代替テキスト( alt属性 )とは画像などの非テキストコンテンツに対して、テキストコンテンツと同様の情報をユーザーに伝えるテキストのことを言います。
画像に代替テキストを設定することは、ユーザーにとっても親切ですし、SEOにも大きなメリットがあります。
それは、クローラーが画像の内容を理解できるようになるため、Google画像検索に検索結果として表示されるようになることです。
すなわち挿入する画像に代替テキストを記述するだけで、検索エンジン( 画像検索 )からのユーザー流入も期待できるということになります。
そのため、画像に関連するキーワードを含みながら、具体的かつ簡潔な文章で入力するようにしましょう。
| <対策方法まとめ>
・画像に代替テキスト( alt属性 )を記述して、ユーザーが分りやすく、検索結果に表示されるようにしよう! |
9. SEO対策③:クローラビリティを考慮しよう!

Googleに高評価されるためのSEO対策、ユーザーの利便性を高めるためのSEO対策についてここまで紹介してきました。
最後は、検索エンジンにとって見つけやすい、理解しやすいコンテンツにする方法を解説します。
もう少し具体的に言うと、Googleのクローラーがサイト内のWebページを見つけて、そのWebページの内容を理解しやすいようにサイト構造を最適化する方法です。
こちらも絶対に外せない項目ばかりで、SEO対策において重要となりますので必ずチェックしましょう!
9-1 内部リンクをしっかり構成する
関連性のあるページを内部リンクとして貼り付けることは、Googleからも重要なページと認識してもらうことに繋がります。
そのためには、まず関連するコンテンツがサイト内に必要となりますし、そのコンテンツの質も重要になります。
ここにはどうしても時間や人的コストがかかりますが、Googleに評価されるためには、コンテンツの充実度は切り捨てることはできません。
関連するコンテンツを増やして、専門性を高めることができれば、内部リンクが構築しやすいだけでなく、Googleから質の良いサイトとして認識されます。
何かに特化したブログではなくても、ブログ内でカテゴリを細分化すれば大丈夫です。
また、内部リンクは元のページに戻りやすいかどうかも大切です。リンク先のページにはリンク元のリンクを貼り付けるようにしましょう。
| <対策方法まとめ>
・リンクは出来れば画像ではなくテキストリンクにし、キーワードを盛りこもう! ・スパム扱いされないよう、リンクテキストは同じ内容を使わないようにしよう! ・コンテンツの最後には関連ページへのリンクも貼り付け、更にテーマ性を強調しよう! ・内部リンクを貼る際は、リンク元ページにも戻れるように相互リンクにしよう! |
9-2 XMLサイトマップを設置する
XMLサイトマップとは、ウェブサイト内の各ページのURLや優先度、最終更新日などを記述したXML形式のファイルのことで、Googleに「 ウェブサイト全体のページ構成 」を伝えるために重要です。
XMLサイトマップを設置するには、「 sitemap.xml Editor 」などの専用ツールを利用して自動作成したXMLサイトマップを自分でサーバーにアップロードしたり、WordPressなら「 Google XML Sitemaps 」のプラグインを導入してXMLサイトマップを設置し、GoogleサーチコンソールでそのXMLサイトマップのURLを送信するという流れになります。
このように、サイト内のコンテンツを検索エンジンに見つけてもらいやすくし、インデックス( 登録 )を促進することが、上位表示を達成するポイントとなります。
まだ作成していない場合は必ず作成しましょう!また、Google Search Consoleからサイトマップ情報を送信するのも忘れずに!
| <対策方法まとめ>
・XMLサイトマップを作成してGoogle Search Consoleから送信しよう! |
9-3 きちんとインデックスさせる
自社のページがクローラーに発見され、評価をしてもらえているかを確認するのもSEOには大切です。
方法としては、Google Search Console上部にクロールされているかを確認したいページのURLをいれ、「 URL検査 」をクリックします。その次に「 カバレッジ 」をクリックすると、「 前回のクロール 」という部分から直近でいつクロールされていたかを確認できます。
また、Google Search Consoleを使用せずに確認したい場合は、確認したいページのURLの前に「 site: 」を入れて検索すると、そのページがインデックスされているかどうかを確認することができます。きちんとページがインデックスされている場合は、検索結果に表示されます。
新規ページはもちろん、内容を変更したページに関してもインデックスされているかどうかを確認することは大切です。
| <対策方法まとめ>
・Google Search Consoleの「 URL検査 」を利用して対象ページが検索エンジンにいつ評価されたかチェックしよう! ・確認したいページのURLの前に「 site: 」を入れて検索し、そのページが登録されているチェックしよう! |
9-4 ページ評価が分散していないかチェックする
Googleでは、ページ内容の重複はマイナス評価になってしまいます。もう少し分かりやすく説明すると、サイトに新規コンテンツを追加していき、その中によく似たコンテンツが2つ存在するとGoogleは類似コンテンツであるとみなし、評価が分散してしまう可能性があるのです。
検索順位がなかなか上がらない場合、キーワードに対する評価が複数のページに分散してしまっていることが原因であることも実際に少なくありません。
少し手間が増えるかもしれませんが、検索順位をチェックする際、対策キーワードのランキングだけではなく、検索結果に表れる自サイトのページの入れ替わりや、複数ページがランクインしている上位になっていないかまで確認するようにしましょう!
| <対策方法まとめ>
・上位表示させたいページが検索結果に表示されているか確認しよう! ・複数のページが同じキーワードでランクインしていないか把握しておこう! |
9-5 URLを正規化する
先ほどのトピックの平行線上にある問題ですが、1つしかないコンテンツでも、別パターンのURLが存在すると、それぞれを別ページと判断され、別々に検索エンジンに登録されてしまいます。
そして何が起こるかというと、先ほど説明したのと同じようにページの評価が分散し、順位にも影響します。
1つのコンテンツで別パターンのURLがある状態とは、「 www 」がついているパターンとついていないパターン、どちらで検索してもそのコンテンツページにたどり着ける場合のことを言います。
サイトの運営側や見ているユーザーにとって、「 https 」か「 http 」か、「 www 」がついているかいないか、などは記述の違いですし、どのようなURLでもそのページを見ることができればそこまで気にしていないと思います。
しかし、検索エンジンは全てのURLパターンを別のページとして認識して登録するため、せっかく質の良いコンテンツでも、そのまま正当に評価してもらえません。
そうした残念な状況を防ぐためにも、「 正規ページURL 」をheadタグ内に記述するようにしてください。
| <link rel="canonical" href="正規ページURL"> |
この対策を「 URLの正規化 」と言います。
| <対策方法まとめ>
* 各ページにlinkタグの「 canonical 」を記述し、URLの正規化をしよう! |
10. SEO対策:番外編

10-1 SNS( ソーシャルネットワーク )を利用する
サイト内のページをFacebookやTwitterなどのSNSでシェアやツイートしてもらうことで、外部リンク( ナチュラルリンク / 外部のサイトから自然に張られたリンク )を獲得する機機会が増えます。
GoogleはFacebookの「 いいね! 」ボタンやTwitterの「 リツイート 」ボタンの動きまで連動して評価できないため、直接的なSEO効果はあるわけではありません。
しかし、実際にユーザーの知り合いに拡散されているので、そのリンクがクリックされればサイトのアクセス数は必然的に増え、間接的なSEO対策となります。
ですので、新しい記事やコンテンツを追加したらどんどんSNSへ公開し、流入経路を増やすようにしましょう!
| <対策方法まとめ>
・SNSで拡散されるとアクセス数が増えるため、間接的にSEO対策になる! |
11.まとめ

いかがでしたでしょうか?
SEOは、ある対策を行ったから順位が上がるという単純な仕組みではありません。Google検索エンジンのアルゴリズムは、200以上の指標を基にページの価値を算出してランキングを決めているからです。
しかし、「 SEO対策 = Google対策 」であることを忘れずに、Googleの方向性に合った正しいWebサイト制作と運営を行っていれば、自然と評価は上がり、順位アップが見込めるようになると思います。
どれだけ探しても、SEOには即効性のある施策はありません。我慢強く地道にサイトを育てていくことで、結果的に大きな成果をもらしてくれるはずです。
さあ皆さん、 本記事で紹介したSEO対策のポイントを抑えて、上位表示からのコンバージョン増加を目指しましょう!
