DXを促進する上で一番重要なのは「 人材 」でしょう。
しかし、経済産業省が発表した「 DXレポート 」内でもIT人材の不足で日本経済が悪化するという内容があります。
DXを促進することを決めても、DXやITを担う人材がいなければDXを促進するどころか始めることも難しくなってしまいます。
反対にDX人材を確保することが出来れば、DXを進めやすくなり、自分がDX人材になる場合には就職や転職がしやすくなるでしょう。
今回の記事では「DXに必要な人材」「 必要な職種6つとスキル 」を中心に解説していきます。
DX人材の重要性やDX人材を目指すために必要なことが分かる内容になっています。
DX人材とは

まずは「 DX人材 」について解説していきます。
DXとDX人材の定義について理解を深めてみてください。
DXについて
DXとはデジタルトランスフォーメーションの略称で、ITやデジタル技術を利用して、社内のシステムの効率化を行い、参入している業界に変革を起こしていくことです。
日本企業の多くは、「 DX=IT、デジタル化 」と考えていることが多いですが、実際にはIT化やデジタル化はDXの一歩目であり一部です。
つまり、経営陣がITやデジタルといった技術を導入してもDXとは言えず、社内全体で取り組むことができなければDXの実現は難しいでしょう。
DX人材の定義
DXは簡単に説明すると、「 データの活用・企業の変革・業界の変革 」の3つになります。
データを蓄積し、データをもとに新しい製品やサービスを生み出すことで、業界自体に変革を起こします。
DX人材は、こういった取り組みを担う中心的な人材になるため、「 ITリテラシーが高い 」「 技術がある 」といった単発的な能力だけではDX人材とは言えないでしょう。
自らDXを促進していける人材こそが、DX人材ということになります。
社内でDXの促進を担う人材
DX人材は1つの職種だけにどどまるのではなく、幅広い視野が必要になります。
DXは社内全体で取り組むため、他部署との連携やシステムの共有が必要になってきます。
企業としてDXを促進していくためには全体の部署で同時に進める必要があるため、DXの専門部署を作ったとしても簡単に促進できるものではありません。
DX人材はDXの専門部署などでDXの促進のみに注力する人材のように思われがちですが、実際には様々な部署でDX人材が必要になってきます。
次の項目でDX人材が必要な職種を解説していきます。
DX人材が必要な職種6つ

DX人材が必要になる職種については、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が6つの職種を定義しています。
特に①プロダクトマネージャーと②ビジネスデザイナーは外注ではなく、社内の人材が必要になるでしょう。
①プロダクトマネージャー
プロダクトマネージャーは「 DXやデジタルビジネスを実現するための人材 」である必要があります。
DX促進の中では中心の存在となるため、管理職以上や部署のエースと呼べる優秀な人材を起用する必要があります。
社内のDXの進行具合を常に把握し、必要な措置をとることになるため、把握力だけではなく、周りからの信頼も必要になるでしょう。
また、DXはITやデジタル技術への投資も必要になるため、プロダクトマネージャーは冷静に社内、社外の状況を把握し実行に移さなければいけません。
DX人材の中でも、スキルだけでは務まらない職種のため、社内の人材から選出することが多くなっている職種です。
②ビジネスデザイナー
ビジネスデザイナーはプロダクトマネージャーに次ぐ重要な人材になります。
「 DXやデジタルビジネス企画・立案・推進 」を行うことになるため、幅広い業務に関わることになります。
顧客のニーズや市場にも敏感に反応する必要があるため、マーケティング能力を持っている人材が望ましいでしょう。
企画や立案も行うため、発想力や企画力を持っていることも重要になってきます。
プロダクトマネージャーと同じく、社内の人材から選出されることが多く、外注や新卒の社員に任せることが少ない職種です。
③テックリード
エンジニアリングマネージャーやアーキテクトとしての役割を担うのがテックリードです。
主に「 システムの設計から実装 」までを行うことになります。
DXに必要不可欠なIT、デジタルという部門を扱うことになるため、プログラミングの技術が必須と言えるでしょう。
エンジニアとしての技術が必要なため、新卒で入社した社員が起用されることはほぼありません。
社内のエンジニアか中途採用で優秀なエンジニアを採用することが多くなっています。
④データサイエンティスト/AIエンジニア
データサイエンティストは「 データの解析・分析が出来る人材 」です。
DXはデータを収集することが重要で、収集したデータから顧客のニーズに答えたり、業種に変革を起こす新しいビジネスモデルを開発していくため、データサイエンティストはDXにおいて重要な職種になります。
しかし、業務としてはデータの解析、分析だけではなく、データを活用していく発想力も必要になるでしょう。
社内のビジネスについても理解していないといけないため、社内で人材の育成をしたり、新卒を一からデータサイエンティストに育てる企業も多くなっています。
中途採用も育成が可能なため、転職でも可能な職種になります。
⑤UI/UXデザイナー
UIとUXはどちらもWebデザイナーに位置付けられることが多くなっています。
UIはWebサイトやアプリの画面に映っている情報を表し、UXは目に見えるものではなく、「 体験 」と表現されることが多いですが、「 改善 」と考えたほうが分かりやすいかもしれません。
UIで得られる情報からより良く改善し、新しいものを生み出すのがUXです。
UI/UXデザイナーはWebデザイナーとして、社内で使用するシステムのデザインや、顧客が使うシステムを使いやすくデザインする人材になります。
DXではITやデジタル技術を活用していく必要があるため、UI/UXデザイナーは必須と言えるでしょう。
もともとWebやアプリの開発を行っているIT企業では自社で完結することが多く、IT関連の企業ではない場合に外注することの多いDX人材です。
⑥エンジニア/プログラマー
「 システムの実装やインフラの構築、保守などを行う人材 」がエンジニアやプログラマーになります。
エンジニアとしてのスキルが必要ですが、多くのシステムに関わるため、SIer(エスアイアー)が一任されることが多いでしょう。
SIerはシステムの構築から実装までの全ての工程を行う企業のことです。
企業としてもばらばらにエンジニアやプログラマーを起用するよりも、SIerに集中させたほうがDXの促進もスムーズになります。
例えば、保守に関しては自社、構築から実装はSIerと分ける企業も珍しくはありません。
IT企業であれば自社の人材から起用し、IT企業でなければ外注することが多い職種になります。
DX人材に必要なスキル

DX人材が必要な職種を紹介してきましたが、DX人材には様々なスキルが必要になることを理解してもらえたはずです。
ここでは、DX人材に必要なスキルを解説していきます。
ITリテラシー
ITリテラシーは「 通信やネットワーク、セキュリティなど、ITに関わる要素 」の知識や能力のことです。
DXとITは切っても切れない関係で、DXの促進にはITリテラシーが必要になります。
ITリテラシーが低ければDXを進めていく中でも、「 可能なものと不可能なもの 」を判断することが出来ません。
他にも、新しいテクノロジーを活用していくこともDXを促進する上で重要なため、AIなどの技術も最低限、理解していなければ自社の強みを活かした新しいサービスを作ることは難しくなるでしょう。
ITリテラシーはDX人材として必要不可欠なものです。
データの活用
DXはデータを収集して活用していくことで最大限に力を発揮します。
反対にデータを活用できなければDXが成功することはなく、失敗に終わってしまうでしょう。
「 DX人材が必要な職種 」で紹介したデータサイエンティストほどの解析や分析能力はなくても、単純なデータの活用が出来たほうがDX人材として必要とされます。
どの職種でDX人材になるにしても、最低限のデータ活用が出来たほうが応用も効きやすくなります。
マネジメント能力
マネジメント能力は主にプロダクトマネージャーとビジネスデザイナーに必要なスキルです。
DXを進めていく上で他部署との連携が必要になってきます。
デジタル専門の部署が立ち上げられている場合には、トップに立つ人間にマネジメント能力がなければ統率が取れずにDXも上手く進まないでしょう。
「 DXは社内一丸となり取り組むもの 」なので、マネジメント能力の高い人材が多いに越したことはありません。
各部署がバラバラに動かないように、マネジメント能力に長けた人材が調整していく必要があります。
マネジメント能力が高ければDX人材としても1つ上に行きやすくなるでしょう。
マーケティング能力
マーケティングは新しい販路や商品、サービスを生み出していくために必要なものです。
DXは業種に変革を起こすものなので、新しいサービスのためにもマーケティングは必須になるでしょう。
プロダクトマネージャーといったDX人材の中でもトップを担う職種であればマーケティング能力は確実に必要になります。
他の職種でもマーケティング能力があれば、必要とされている以上に活躍することが出来るでしょう。
DX人材に必要な思考と行動
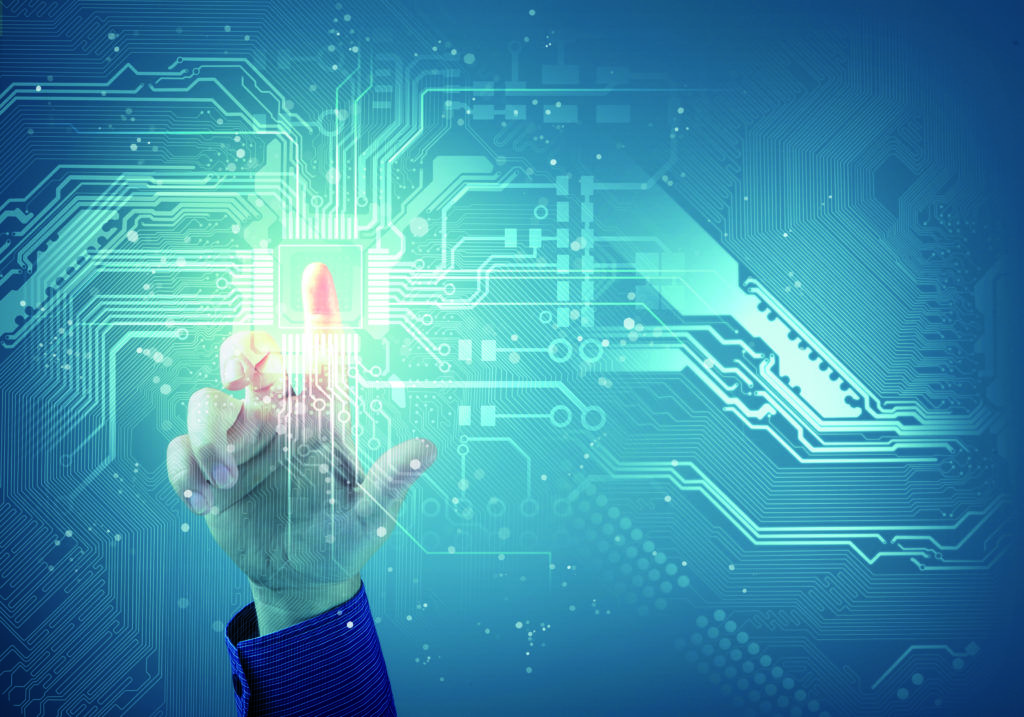
DX人材には必要な思考と行動があります。
これからDX人材を採用、起用する企業は選考の基準にし、DXを目指す人は参考にしてみてください。
課題の発見と解決
DXを促進していくためには、自社や業界の課題を発見することが重要になります。
「 顧客中心 」がDXの基本になるため、顧客が抱えている課題を発見し、解決することで新しいビジネスモデルの構築が可能になります。
また、自社内でもDXの促進を妨げている課題や、さらに促進につながる課題を発見することは、どの部署においても必要なことです。
自ら課題を発見し解決に向けることが出来る人は優秀なDX人材と言えるでしょう。
新しいことへの挑戦心
DX自体が日本での歴史は浅く、経済産業省が2018年に発表した「 DXレポート 」から始まっています。
手探りで進めいている企業も多く、DX人材はその中心となってDXを促進しています。
DX人材は新しいことへの挑戦が常に必要となり、現状に満足することなく進む必要があるでしょう。
多くの人は挑戦よりも安定に向かうことが多いため、反対に新しいことに挑戦し続けることは難しいこともあるはずです。
しかし、DX促進の中心となるからには、現状に満足せず、常にアンテナを張りながら動いていく必要があります。
コミュニケーション能力
DXは1人でも部署でも完結するものではありません。
企業に属している全ての部署が協力をしてDXを促進していくことになります。
特に、プロダクトマネージャーやビジネスデザイナーは全部署と連携してDXを促進していくため、コミュニケーション能力が必要になるでしょう。
周りの人や部署を巻き込みながら進めることで、DXは飛躍的に進む可能性を秘めています。
コミュニケーション能力を高めることで他部署とも連携を取り、DXの促進に拍車をかける存在となる必要があります。
デザイン思考
デザイン思考はデザイナーの思考というわけではありません。
デザイン思考とは「 一連の問題解決 」のことを指します。
AppleやGoogleも採用している思考方法で、重要なのは自分が「 ユーザーである 」と考えることでしょう。
まず、仮設を立てて実行し、最初には明らかになっていなかった問題点に対して解決策や代替案を考えていきます。
基本的には「 仮設や検証を重視する 」ということです。
DXは基本的に顧客中心となるため、デザイン思考はDX人材に必要な思考と言えるでしょう。
DX人材を育成するポイント

既存の社員や新卒、中途採用でDX人材を育成するためのポイントを解説していきます。
参考に採用や育成を進めてみてください。
採用時点での見極め
まずは、「 採用時点での見極め 」です。
新卒、中途採用向けになります。
主に見極めるポイントは下記の2つになるでしょう。
①コミュニケーションが得意
コミュニケーション能力はDX人材に必要不可欠です。
DXは1人で進めるものではなく、部署、会社全体と大規模で進めるものです。
他部署とも円滑にコミュニケーションが取れなければDX人材には不向きでしょう。
②自主的
DXの促進には自分で新しいことを考えて行動する自主的な性格が必要です。
言われてから動くようなタイプはDX人材には不向きでしょう。
営業・マーケティング部門から選出する
DX人材には発想力や企画力が重要になってきます。
営業やマーケティング部門がある場合には、これらの部門に所属している人材から選出すると育成もしやすいでしょう。
営業は外部や顧客とのやりとりが多いため、コミュニケーション能力が高い人材が多くなっています。
また、マーケティング部門であれば、新しいサービスや製品を企画することに優れている人材が多いため、発想力だけではなく、企画力もあります。
自社に2つの部門がある場合にはDX人材選出の対象にすると良いでしょう。
DXの経験者と共にプロジェクトを進行させる
DXと一切関わりのない人材を育成していく最大のポイントは「 経験者と共にプロジェクトの進行をさせる 」ことです。
特に新卒であればDXの経験者と一緒でなければ、難しい業務内容とストレスを与え続けることになるでしょう。
自社にDX人材が1人もいない場合には、まずはDXの経験者を自社に採用する必要があります。
「 経験者と共にプロジェクトの進行をさせる 」ことは既存の社員でも、新卒、中途採用でも必要になります。
DX人材を自社で育成するメリット

DX人材はすでに実績のある人材を中途で採用したり、外注することもあります。
しかし、自社の人材であれば、すでに自社のシステムや企業理念も把握しているため、育成したほうが自社に合うDX人材が出来るでしょう。
DX人材を自社で育成するメリットについて、いくつか解説していきます。
自社のシステム・方向性を理解している
既存の社員からDX人材を育成するメリットの1つが、「 自社のシステム・方向性の理解 」です。
DXは企業の事業をまるごと変えるわけではありません。
あくまで既存の業務改善や、自社のサービスをより活かすための変革を行うことになります。
既存の社員であれば、既存のシステムも理解しているため、問題点や改善点という部分に着目しやすく、DXも進みやすくなります。
社外からDX人材を採用する場合には、自社の既存システムや方向性を一から理解してもらう必要があり時間がかかるでしょう。
自社内でDX人材に向いた社員を選出し、DX人材として育成するほうがDXは促進しやすくなります。
一貫性を持ってDXを促進することが出来る
特にシステムに言えることですが、新システムを外注する場合にはエンジニアの技術やコストの面で、一貫性を保つことが難しい場面も出てきます。
しかし、自社内で企画からテスト、実装まで行える人材がいれば、システムとしても一貫性を持ってDXを促進することが出来ます。
また、DX人材の中心である、プロダクトマネージャーやビジネスデザイナーを外注してしまうとDXの進行具合も分かりにくくなり、一貫性は保てないでしょう。
DXは全ての部署が連携をとりながら進めていく必要があります。
一番の理想はDXに関わる全ての人材を自社内で育成することです。
DX人材を自社内で育成することができれば、一貫性を持ってスムーズにDXを促進することが出来るでしょう。
DX人材を採用する際のメリットと基準

次に「DX人材を採用する際のメリットと基準」を解説していきます。
メリット
一番のメリットは「 即戦力 」という部分になるでしょう。
育成であれば社内で研修を行う必要があり、人も時間も割くことになります。
しかし、DX人材を採用すれば、最初からスキルのある人材を選ぶだけです。
自社のシステムに慣れてもらう必要はありますが、元のスキルがある分、研修などは短期間で終了するでしょう。
即戦力となるDX人材を採用することが出来れば、いち早くDXを促進していくことが可能になります。
コミュニケーション能力の高さ
まず、DXは社内全体で取り組むため、部署ごとの連携が必要になります。
特にDX人材ともなれば、DXを促進する中心人物になるため、各部署、人とスムーズに連携を取る必要があります。
DX人材を採用するポイントとしては「 コミュニケーション能力の高さ 」が重要になるでしょう。
例えば、面接でも自分から話すことや質問がないのであればDX人材としては向いていないかもしれません。
積極的に人と関わろうとし、無難に会話もこなせるようなコミュニケーション能力があるのかどうかを見極める必要があります。
柔軟な思考
DXは促進していく中で様々な変更点が加えられることがあります。
例えば、DXの全体像を決めるロードマップの作成は大切ですが、全てがロードマップ通りに進むことはないでしょう。
途中で変更が必要になった時、柔軟に対応できる思考が必要です。
言われたことしか出来ない、考えられないというのであればDXには向きません。
DXを促進していく人材は、変更や行き詰まった時にも柔軟に対応できる思考を持っている必要があります。
率先する行動力
DXは変革を起こすための動きなので、毎日、同じことを繰り返すルーティンが好きな人には向いていません。
特に、DXは部署ごとだけではなく、全体を通して進めていくため、率先して自らが行動する力が必要です。
周りの人や部署を自ら巻き込みながらDXを促進していくような人材を採用しましょう。
面接の時は自ら発信する人材を見極める必要があります。
聞かれたことに答えるだけではなく、自ら考えて疑問を投げかけてくるような人材が好ましいです。
DX人材になるためのポイント

この項目では、「 DX人材になりたい 」という人向けに解説していきます。
企業によってはDXに関わることが未経験でも他に特記すべきスキルがあればDX人材として採用することもあります。
IT関連の資格を取得
DX人材として企業に採用されるためには部署に関わらず、最低限のITリテラシーが求められます。
企業に「 DX人材に適している 」と判断されるために一番良いのはIT関連の資格を取得しておくことでしょう。
IT資格は幅広い種類がありますが、特にIT関連未経験なのであれば、「 ITパスポート 」「 基本情報技術者 」の取得が近道です。
特に、ITパスポートはIT資格の中でも合格率は高く、企業からも「 ITリテラシーの高い人材 」と判断されやすくなるのでおすすめです。
企業側もDX人材を必要としている分、IT未経験の人材を採用することは難しい選択になるため、出来る限り証明できる資格を所持しているほうが有利になるでしょう。
DXを促進しているベンダー企業へ就職
ベンダー企業とユーザー企業の違いについては次の項目で解説しますが、DX人材になるのであればベンダー企業に就職するのが近道でしょう。
現在、DXを促進している企業は一般の人でも知っているような企業が多いですが、DXの中心になるシステムを取り扱っているわけではないため、DX人材も経験者を中心に集めています。
しかし、ユーザー企業であればシステムを納品する側になるため、一からエンジニアなどのDX人材を育成しています。
最終目標がユーザー企業である場合でも、まずはベンダー企業で実力をつけることで、ユーザー企業に移りやすくなるでしょう。
ベンダー企業とユーザー企業の違い
ベンダー企業とユーザー企業の違いを簡単に説明していきます。
・ベンダー企業
主にユーザー企業に対して製品やサービスの提供をしています。
代表的な企業では、NTTやNECが分かりやすいでしょう。
2社ともインターネットに関わるサービスを提供することを主としています。
・ユーザー企業
消費者に対する事業展開をしています。
DXの代表例でよく上がるAppleなどは消費者に対して製品やサービスの販売を行っているため、ユーザー企業となります。
ベンダー企業は多くの社員がDX人材である必要性を持ちますが、ユーザー企業の場合は少数のDX人材しか必要ないということになるでしょう。
日本はDX・ITの人材不足

経済産業省が「 DXレポート 」で日本経済の悪化を提唱していますが、原因の1つに「 DX・IT人材の不足 」があげられます。
現状
DX・ITの人材不足の大きな原因として、少子高齢化があります。
今までに現役で活躍してきたIT人材が定年を迎え、少子化が進むことで人材も不足することになります。
特にIT関連の産業は年々増加傾向にあるため、必然的にIT人材も不足していると言えるでしょう。
このまま人材不足が進めば2025年以降に日本は年間12兆円の経済損失を生むことになります。
打開策として進められているのが、システムを新しくすることで業務を効率化したり、今までになかったサービスを生み出すDXになります。
課題と対策
DX・IT人材不足の課題としては、「 IT人材を育成すること 」でしょう。
このままでは2030年には約38万人のIT人材不足になると予想されています。
少子高齢化でそもそもの分母が少なくなってしまうのは仕方のないことです。
しかし、DXを促進するにあたってIT人材が必要になるのも事実なので、国だけではなく企業としても対策を取る必要があるでしょう。
IT業界に憧れる人は多いですが、就職や転職のハードルが高いために諦めている人が多いのが現状です。
日本全体でIT人材を育成していくことが、人材不足の解消につながるでしょう。
まとめ
今回の記事では「DXに必要な人材」「 必要な職種6つとスキル 」を中心に解説していきました。
日本はDXを促進する必要があり、そのためにはDX人材が必要不可欠です。
DX人材は採用も育成も簡単なものではありませんが、DXを促進していくためには欠かせない人材となるでしょう。
今回の記事を参考に「 DX人材の採用・育成 」「 DX人材を目指す 」ことに挑戦してみてください。
