数ある電子契約サービスの中で、どのサービスを選んだら良いのかわからないという方は多いでのはないでしょうか。
そこで、本記事では国内シェアの大多数を占める「 クラウドサイン 」について説明していきます。
シェアの多数を占めていると言われる「 クラウドサイン 」ですが、デメリットや問題点はないのか気になりますよね。今回、デメリットや問題点についてもしっかり調べたので参考にしてみてください。
クラウドサインとは

「 クラウドサイン 」とは、先ほども説明した通り、電子契約締結サービスの1つ。
弁護士ドットコムが運営しており、業界シェアは80%とのこと。法律相談ポータルの運営を行なっているなど、法律についても信頼できそうですね。
直近開始されたサービスというわけではなく、2015年10月よりサービスを開始しています。需要が高まっているよりも前からサービスが存在していることが、支持されている要因と考えられます。
クラウドサインの概要
クラウドサインでは、契約に必要なステップを全てインターネット上で解決できます。
例えば、企業間での請求書や契約書などの交付の際に利用し、クラウドサイン上で「 電子署名 」と「 電子サイン 」を使うことで証明を行うことが可能。
確かに、書面での契約に必要な押印・郵送・管理が全てインターネット上で作業でき、大幅なコストカットが可能となっています。
そもそも、電子契約の流れがあまりわからない方に向け、電子契約のフローについて説明します。
電子契約では、今まで書面で実施してきた契約をインターネット上で完結することが可能。契約締結後の保管や更新もできます。
書面での契約締結に必要な捺印は、先ほど簡単に触れた「 電子署名 」や「 電子サイン 」が代替となります。
そもそも、電子契約自体に法的根拠はあるのか、改竄のリスクはないのか、といった疑問がある方もいるのではないでしょうか。
電子契約については、電子署名法などできちんと定義されており、法的根拠を持っています。
さらに、大抵の電子契約サービスはタイムスタンプというシステムを利用しており、後日改ざんしたとしても証拠が残るようになっています。
これらの説明から、電子契約がリモート環境に適していることがわかるでしょう。昨今、電子契約の導入が増えたことにも頷けますよね。
関連記事:電子契約システム「クラウドサイン」とは?評判・導入メリットを解説
クラウドサインのデメリット
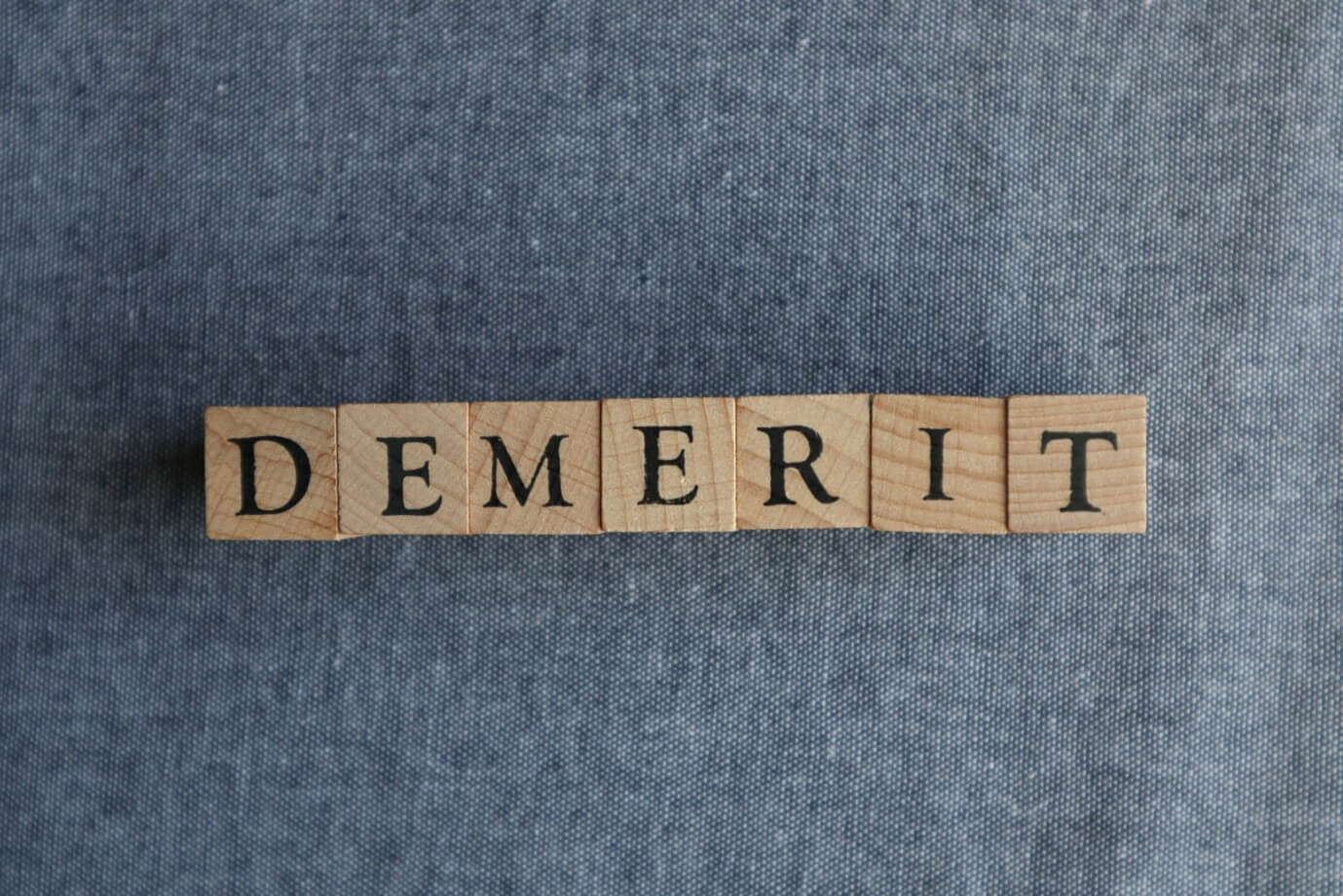
先ほど、「 クラウドサイン 」は業界シェアの大多数を占めると説明しました。そんなクラウドサインですが、問題点やデメリットはないのでしょうか。
また、どんな人にも適しているサービスと言えるのでしょうか。そういった疑問を解決するべく、クラウドサインについて調べてみたため詳しく説明していきます。
費用が高い
まず、クラウドサインの課金制度についてデメリットがありました。このデメリットの説明の前に、課金制度を簡単に説明します。
クラウドサインにはいくつかの料金プランがあります。課金プランは3つ。無料で利用できるお試しプランも存在します。
Standard
まずは最も安い値段で利用できるプラン。こちらは月額10,000円で、基本的な契約書の作成や締結が可能です。
Standard plus
続いては月額20,000円のプラン。こちらは、Standardプランの機能に紙書類のインポート機能が追加されています。もともと締結していた契約の保管や更新ができるようになります。
Business
最後は、月額100,000円のプラン。金額が跳ね上がった分、アカウント登録やIPアドレスの制限などが可能となり、セキュリティが強固になるようです。
クラウドサインには、こういった3つのプランがあるのですが、全てのプラン共通の料金設定が存在しています。実は、この中にデメリットがあるのです。
共通の料金設定における最大のデメリットとは、契約の送信ごとに200円の料金がかかる点。つまり、契約を締結するごとに料金が発生するのです。
課金のタイミングは書類を送信した時となるため、契約内容に不備があり、契約書を取り下げたい場合や、受信者のメールアドレス間違いなどで届かなかった場合も送信したとみなされます。
先ほど説明した各プランの金額は、利用できるサービスの範囲に応じ段階ごとに用意されていたにすぎません。どのプランでも一律で上記の送信料金がかかります。
また、無料で利用できるプランでは、月間5件までの契約締結が利用可能。ただし、こちらのプランでは電子署名の有効期限が1年となっており、実質1年しか利用できません。
入力作業が煩雑
料金の他にも、契約書の入力作業が煩雑だという声も上がっています。なんと、10項目以上もの入力が必要だったり、修正の際にも一手間があるようです。
さらに、備考の入力欄の設定が難しいという声も。慣れるまでは、入力作業にも手間がかかるということです。
また、フォルダを分けて閲覧を制限する、という機能は搭載されていません。
大きな会社であればあるほど、部署やプロジェクトごとなどのフォルダ分けは必須。そちらに対応できないとなると、セキュリティ面でも不安になりますよね。
承認権限の設定や制限の設定は、Businessプランであれば設定できるようですが、それでもフォルダ分け機能はつかないということで、少し不満が残るかもしれません。
PDFにしか対応していない
契約書類としてアップロード可能なファイル形式が、PDFのみである点もデメリットの1つ。契約書の作成に、PDFツールが必須となってしまいます。
WordやExcelには対応していないため、気軽に契約書の作成や修正ができない点は問題だと言えるでしょう。
デメリットを解決できるサービスNINJA SIGN

ここまで、クラウドサインについて説明してきました。業界シェア80%を超えるクラウドサインといえども、デメリットが少なからずあることがわかりましたね。
現在は、これまで以上に電子契約サービスが増えており、内容もなんとなく似たり寄ったりに思えてしまいます。
やはり、できるならクラウドサインを利用したいですよね。そこで今回は、先ほどあげたクラウドサインのデメリットを解消するサービスを紹介します。
NINJA SIGNの概要
今回紹介するのは「 NINJA SIGN 」。2019年に開始したサービスのため、比較的新しいサービスと言えます。
運営会社は株式会社サイトビジット。この会社では、「 資格スクエア 」というオンライン×リアルの資格予備校の運営も行っています。
代表取締役は現役の弁護士とのこと。弁護士が開発に携わっているとなると、安心感がありますよね。
そんな「 NINJA SIGN 」ですが、実際にどういったサービスであるか、先程紹介したデメリットをカバーできるような部分に焦点を当てて、説明していきます。
料金が安い
「 NINJA SIGN 」は、料金が非常に安いと言われています。
フリープランがあり、従量課金制ではあるという点はクラウドサインと同様。ただし、最も安いプランは4,950円です。料金について、もう少し説明していきます。
Light
こちらのプランが、最も安い4,950円のプラン。送信件数に限りはあるものの、50件と十分な量となっています。
Light Plus
続いては、19,800円のプラン。登録可能なアカウント数が6アカウントまでと増え、送信件数も無制限となります。約2万円で送信制限がなくなる、と考えると非常にお得なプランになっています。
Pro
次は50,000円のプラン。この時点で、使用できる機能の全てが利用可能となっています。
Pro Plus
最後のプランは月額120,000円のプラン。こちらのプラン、機能としてはProと変わりません。
しかし、登録可能なアカウントが100までと非常に多く、アカウントの追加費用もすべてのプランの中で最も安くなっています。
ここまでが、「 NINJA SIGN 」の料金の説明です。ここで「 クラウドサイン 」での料金形態を思い出してみましょう。デメリットとして、送信費用が逐一かかる点が挙がっていました。
しかし、「 NINJA SIGN 」では最安値がさらに安く、送信費用もかかりません。個人事業主にとっては、非常にありがたい料金形態になっていますね。
また、小刻みにプランが分かれており、どんな事業規模の企業でも取り入れやすい形になっています。
PDF以外にも対応
続いて、利用できるファイル形式についても説明します。「 NINJA SIGN 」では、PDFの他にGoogleドキュメントにも対応しています。そのため、契約書の作成や修正が簡単にできます。
「 クラウドサイン 」ではPDFしか対応していないため、修正の際、非常に面倒な作業になってしまうと説明しました。「 NINJA SIGN 」ではそのデメリットが解消されています。
また、実はその他の電子サービスでもGoogleドキュメントに対応しているものは少なく、他サービスにない機能として、比較の鍵となるかと思います。
ワークフロー機能の搭載
「 NINJA SIGN 」には、「 ワークフロー 」と呼ばれる機能が備わっています。※こちらは、Pro以上のプランにしかついていない点に注意してください。
この機能では、契約書の作成ごとに、作成者や契約書のレビュー者、承認者などを設定することが可能。
この機能を利用すれば、契約締結のステップを全てサービス上で完結できるわけです。契約締結時のステータスも表示されるため、進捗を追いやすいというメリットもあります。
さらに、ワークフローへのファイル添付も可能。承認者が設定できるため、他の無関係な社員から閲覧されることも防げます。セキュリティ面でも安全と言えるでしょう。
もちろん、フォルダでの管理機能やアクセス権限の設定も可能。これらは、「 クラウドサイン 」にはない機能です。
ワンストップで締結できると謳っている分、一元化できるための機能がしっかり備わっていることがわかりますね。フルリモートの企業でも導入しやすくなっています。
この他にも、契約書の締結する相手が契約書の修正をできる、紙で締結済みの契約書も管理可能といったメリットもあります。
このように「 NINJA SIGN 」には多くのメリットがあるのです。
関連記事:電子契約システムを徹底比較!NINJA SIGNとクラウドサインの違いとは
まとめ
ここまで、「 クラウドサイン 」のデメリットやそれを解決する「 NINJA SIGN 」の、メリットについて説明してきました。ここで、再度それぞれの特徴をまとめておきます。
クラウドサインのデメリット
- 契約書の送信ごとに費用がかかるため、修正が重なるとその分余分な費用がかかる。
- 入力作業が煩雑で、慣れるまでに時間がかかる。
- フォルダ分けができないため、第三者でも契約書を確認できてしまう。
- PDFにしか対応しておらず、契約書の作成や修正に手間がかかる。
NINJA SIGNのメリット
- 課金制度の内容が柔軟で、どんな規模の企業でも導入がしやすい。また、最も安いプランがクラウドサインよりも安価。
- PDF以外に、Google ドキュメントに対応しているため、Word上で契約書の作成が可能。
- ワークフロー機能によって、承認者の設定が可能。そのため、NINJA SIGN上で契約に必要なステップが全て完結できる。
このように、業界シェアの高いクラウドサインにもデメリットがあることがわかりました。電子契約サービスは、同じように見えても実は細かいサービス内容はさまざま。
当然、企業によってもどういった電子契約サービスが合うかは変わってきます。そのため、サービス検討の際はできるだけ多くの情報を集めておくと良いでしょう。
それでは、本記事の内容を参考に、電子契約サービスを検討してみてくださいね。
