日本国内で現在、閲覧できるホームページは数え切れません。世界で最も人気の高いホームページ作成ツールであるWordPressを用いて作成されたものだけを数えても、国内のホームページ数は520万強。
あなたの担当するホームページをその中からユーザーに見つけてもらうには何かしらの工夫が必要となります。
あなたのホームページにはターゲットのユーザーがアクセスしているでしょうか。
ホームページを閲覧することで商品やサービスの魅力に、ユーザーが触れられるコンテンツ( 掲載している文章や画像といった内容 )となっているでしょうか。
この記事ではホームページの集客について紹介します。ホームページで集客するコツを理解し、ホームページをあなたのビジネスの効果的なツールにしましょう。
ホームページ集客の施策を検討する前に確認すべき事

ホームページへのアクセスというユーザーの具体的なアクションを求める前に、ホームページの役割について確認しましょう。
まず、ホームページ集客でうまくいかない理由は以下のことが挙げられるでしょう。
- ホームページの到達目標がない
- ホームページにアクセスして欲しいターゲットを決めていない
- 商品やサービスの説明がターゲットに向けた表現ではない
- 更新しづらいホームページになっている
次の項目では上記4点について詳しく説明します。
ホームページの到達目標を定める

ホームページで集客するには、具体的に数値化することが大切です。
例えば「 見込み客の獲得 」や「 商品やサービスの売り上げ 」です。
「 獲得 」を目標とする場合は何をもって獲得とみなすか、まで定めましょう。資料請求や新規会員登録の数などがそれにあたります。
「 売り上げ 」の場合は、どの商品の売り上げを増加したいかまで詳細だと、後々の効果判定が行いやすくなるでしょう。
高額商品や定期購入の販売の場合には購入までの検討期間が長くなりがちなので、「 見込み客の獲得 」をまずは目指す方が無理のない流れといえます。
ホームページにアクセスして欲しいターゲットを詳細に設定する

あなたの商品やサービスを購入して欲しいユーザーを決めましょう。そのユーザー像を仮想の人物として、細かく設定したものをペルソナといいます。
実際のユーザーとしては居住地や年齢、職業などはバラバラで幅広い方があなたのホームページに来ることでしょう。
ただ、全方位に響く発信をしようとしてしまうと、抽象的でいろいろな解釈が出来る言葉を選ばざるを得なくなります。そうなると伝えたいことが伝わらない結果となります。
ユーザーの中でも最も重要な人物像に落とし込むことで、余分な情報はそぎ落とされて、伝えるべきことだけが残り、ユーザーにとって分かりやすい情報発信となるでしょう。
ペルソナに響く魅力を定義する

ペルソナが設定できたら、次はそのペルソナにどんな言葉で商品やサービスの魅力を伝えるべきか考えていきます。
例えば、健康に配慮したお菓子を販売するとしたら、栄養素が多く取れることを謳うべきなのか、それとも不要なものが含まれない厳選された素材を謳うべきなのか、どちらが良いでしょうか。
その選択をペルソナが求めている方で訴求すべきです。
購買までの、ユーザーの行動・思考・感情の浮き沈みを言語化するカスターマージャーニー調査を行うと、購入の時点で必ず一度ストレス度が上がります。
なぜなら、誰しも代金を支払うということに少なからず負担を感じるからです。
購入におけるストレスを軽減するのは、ユーザーが購入に魅力を感じた時です。その商品やサービスを手にすることによって、ユーザーが今抱えている悩みや気がかりを解決すると知った時です。
ユーザーは購入すべき理由を求めています。ペルソナにそれらが誤解なく伝わるよう、ホームページに掲載する商品やサービスの説明ワードを選別しましょう。
ここで決めたことがホームページにてメインで訴えるキーワードとなります。
更新しやすいホームページにする

ビジネスでは目標を達成するために、問題や課題を抽出して改善策を講じるというサイクルが繰り返されていると思います。ホームページも同様です。
更新とは改善行動。しかしながらホームページを作りっぱなしで更新していない会社は意外と多いのです。
その理由のひとつに社内での更新が難しく都度、経費が掛かるといった、ホームページ管理体制の問題があげられます。
更新が社内でも委託先でも、それはどちらでも構いませんが、更新は頻繁にあるという前提でのホームページ管理体制を整えましょう。
ホームページの概要がまとまりましたら、いよいよ集客策を実行していきましょう。
SEO( 検索エンジン最適化 )で集客する

GoogleやYahoo!など検索エンジンを使ったインターネット検索の結果であなたのホームページが上位に表示されると、よりクリックされてアクセスするユーザーが増えます。
この検索からの流入を増やす活動をSEO対策といいます。
SEO対策の手順を簡単にまとめました。
- アクセス解析を行う
- 検索に用いるキーワードを設定する
- 検索意図を組んだコンテンツを作る
- 効果を分析して改善する
それぞれの手順についてみていきます。
アクセス解析を行う

アクセス解析はホームページにアクセスしたユーザーの性質を理解し、行動を分析すること。
Googleが提供するアクセス解析ツールであるGoogleアナリティクスの利用が便利です。無料の範囲で様々な機能を使えます。
アクセス解析でチェックして欲しいことが以下の項目です。
- セッション:アクセス数
- ユーザー:アクセスしたユーザーの数
- ページビュー数:ページごとの表示回数
- ページセッション:1回のアクセスで何ページの閲覧があったか
- 平均セッション時間:ユーザーのホームページ滞在時間
- 直帰率:アクセスしたその1ページしか閲覧しなかったユーザーの割合
- 新規セッション率:初めてアクセスしたユーザーの割合
- 流入経路:検索エンジンなのか、広告をクリックしたのか、SNSなのかといったどこからユーザーがホームページへたどり着いたかの経路
- 流入キーワード:アクセスしたユーザーが検索ボックスに入れたワード
アクセス分析
現時点でホームページへとアクセスしているユーザーがどういった理由でそのキーワードを検索に用いたのかを知るためです。
ページ毎の表示回数
人を呼び込めているコンテンツが分かります。離脱が多いページがあれば、そのページはユーザーの検索意図に答えられていない内容だということ。
流入経路
SNSの投稿がユーザーを引き付けたのか、それとも広告によって、もっと知りたいと興味を触発できたのかといった、ユーザーにとっての価値ある情報が何であるかを知ることができます。
インフルエンサーのTwitterへの投稿がきっかけとなっているかもしれませんし、テレビのニュースからかもしれません。
滞在時間と直帰率
より長い時間をかけて閲覧されたページにはユーザーに必要な情報が書かれていたのでしょう。
逆にホームページから離れる人が最後に閲覧していたページには、ユーザーに自分にはあわないと思われた可能性が高いです。
新規セッション
確認すれば、現状のホームの新規ユーザーが獲得できているかの指標となるでしょう。
流入キーワード
最もわかりやすく活用しやすい項目です。検索に用いられることが多いワードはあなたのホームページにユーザーが求められている要素だからです。
ただ、現在はこの流入キーワードは、検索エンジンのほとんどが暗号化したことによって、Googleアナリティクスでは表示できない割合が大きくなっています。
よって、その他のデータよりユーザーの興味の対象を分析して推測する必要があります。
このようにアクセス解析することで、現段階でのあなたのホームページのユーザーについて理解が深まります。
検索に用いるキーワードを設定する

アクセス解析で現段階での検索ワードが想定できたら、続いては設定したペルソナが検索に用いるキーワードが乖離していないかチェックしましょう。
アクセス解析によって、企業側では気づかなかったユーザーの要望を知ったかもしれません。
そういった新しい情報は、ペルソナの興味を引くために作ったキャッチコピーや商品説明文の改善に役立てることができます。
アクセス解析によって、商品やサービスの魅力を伝えようと新商品を出しているのに、ホームページへアクセスするユーザーにはそれが届いていないことに気づけたかもしれません。
ここではSEO対策の前段階に定めたホームページの目標やペルソナを、アクセス解析結果を踏まえて、もう一度見直すパートだとお考えください。
ここでメインに狙うキーワードを再度検討し、決定してください。
検索意図を組んだコンテンツを作る

キーワードを決めたら、次にペルソナがそのワードで検索をおこなった理由を検討しましょう。どんな場面で何を知りたいと思い検索したのか、ということです。
その答えをコンテンツとして、画像化や文章化します。その際に気を付けていただきたいことが3点。
掲載する情報にオリジナリティがあり、権威づけされていて、専門的な内容にすることです。
これらは国内の検索エンジンのシェアNO.1であるGoogleが公表している検索順位に対する評価基準です。
ペルソナの作り込みが深く行われていたら個性は十分に出せると思います。権威づけとは記事の作者が明記されており、その作者が該当分野で社会的な地位があることを指します。
専門性とは妥当性でもあります。そのコンテンツの作り手として納得がいく立場にいて、該当分野での知識に長けていることが明らかであるコンテンツです。
効果を分析して改善する

コンテンツを公開したらまたアクセス解析を行います。想定した通りのユーザーが想定した通りのキーワードであなたのホームページにアクセスしているでしょうか。確認してみましょう。
とはいえ、そう簡単には通らないのが実情です。分析し、コンテンツをリライトして改善。
更にまた分析と繰り返していくことで、ペルソナに響くコンテンツがあなたのホームページに蓄積されていくことになります。
SEOで上位に上がりにくい状態3例

- 更新頻度が少ない
- アクセス解析をしていない
- ホームページ以外の企業活動を考慮していない
企業やブランドへの好感度調査を実施する際に調査の選択肢に入るワードの中に「 その企業には活気を感じますか( イキイキしていますか ) 」があります。
人間はアクティブなものへ魅力を感じやすい傾向を持っています。生命力がある、信頼できると感じるのです。
ホームページにおけるアクティブな状態とは、情報発信や更新が行われている状態。よって、更新が滞っていると感じるページにはユーザーが集まらなくなります。
またSEO対策手順の中にアクセス解析を含めていますが、これを省いてコンテンツは投稿し続けているホームページもあります。
ご存知の通り企業活動はホームページだけに限りません。例えばテレビで商品やサービスが紹介された場合には、突如、ページビューが伸びることがあるでしょう。
新店舗のオープンの際にホームページのQRコードを入れたダイレクトメールを配布したために新規セッション数が増えることもあるでしょう。
そういったホームページ以外の施策での集客のタイミングを、活かせる活動がホームページ上で行えなければ、上位表示を安定的に獲得することが難しくなります。
WEB広告で集客する

ひとつ前の項目でお伝えしたSEO対策は効果が出るまでに少々、時間を有する施策になります。もしあなたが集客を急ぐのであれば広告をWEB上に展開するという手法があります。
ホームページへユーザーを呼び込むためのWEB広告の中で代表的なものを3つご紹介いたします。ただ、広告においても実施後の効果分析と検証は欠かせません。
ユーザーのホームページへのアクセス状況を掲載内容、展開場所と表示タイミングを紐づけて分析します。
その検証を繰り返し、アクセスという行動変容を正しく促せているかの確認を忘れてはいけません。
リスティング広告

指定したワードで検索をかけたユーザーにだけ表示させる仕組みの広告です。
リスティングは定められた条件でリストアップするという意味の単語であり、まさにあなたのホームページのコンテンツに興味がありそうなユーザーだけを抽出する広告となります。
検索エンジンを使用していると結果のリスト上部や下部に「 広告 」マークがついているホームページがありますね。これはリスティング広告として表示されているものです。
リスティング広告は指定する検索ワードによって金額が異なります。より多くの人が検索しそうなワードは高価。そしてクリック単位です。
国内トップシェアの検索エンジンGoogleの広告の場合、使用したいワードのクリック単価は、Google AdWordsのサービスである「 キーワードプランナー 」にて概算ですが知ることが出来ます。
SNS広告

FacebookやTwitter、Instagram、LINEといったSNSが広告掲載先。投稿と投稿の間に紛れ込ませて広告を表示します。
SNSにはユーザーの登録している基礎情報を有していることが特徴。それら情報をもとに広告の配信先の選定が可能です。狙ったペルソナに広告を届けやすいという強みがあります。
ユーザーからしても広告が自分個人へのアプローチという様相を呈して受け止められる点は他の広告とは異なる特徴でしょう。
ディスプレイ広告

画像や動画といったビジュアルを使用し、特定のホームページの広告枠に表示させる広告。
ニュースサイトやまとめサイト、ショッピングサイトなどを閲覧している際に上部や下部、それからサイドバーに広告が出ている表示を日常的に見かけられていると思います。
リスティング広告と同様にクリック単価でも運用できますし、また表示回数で運用もできます。
ちなみにGoogleはGoogle ディスプレイネットワーク( GDN )、YahooではYahoo ディスプレイアドネットワーク( YDN )というサービス名称。
ディスプレイ広告の場合は雑誌や新聞に広告を掲示するのと似ていて、広告に触れるユーザーはそのサイトにアクセスしたユーザーとなります。
よって、興味のあるなしでは対象が絞られません。認知を拡大したい際に取りたい手法です。
広報活動で集客する

マスコミやメディアは多くの人に役立つ情報、もしくは知らない人が多いけれど知っておくべき情報など、公共性と社会性の高いものをニュースという形で世間に知らしめる活動をしています。
ニュースにてあなたの担当する商品やサービスを紹介してもらうことが出来たら、多くの人にその情報が伝達します。ユーザーの興味が喚起されホームページへのアクセスはふえることでしょう。
そのために行うのが、プレスリリースやニュースリリースといった情報発信です。あなたのホームページで扱う商品やサービスにおいて、社会に注目を得られそうなニュースがあった際に行います。
新商品や新サービス、新機能を追加したリニューアルのタイミングには一般的に行われます。業績が好調であることを発信するのもいいでしょう。
その際は社会背景を交えた発信を心がけましょう。例えば新商品であれば開発意図があり、それはユーザーのニーズもしくはシーズに答えたものでしょうから、現在の社会を反映した情報といえます。
割引や特典の付くキャンペーンもユーザーにとってはお得な価値ある情報ですから発信したいですよね。なぜいまキャンペーンなのかその背景を盛り込めば社会的なストーリーを持った内容となります。
ただ、何でもリリースを発信すればよいわけではありません。マスコミやメディアにとって無意味な発信が続くと、そもそも価値ある情報を届けたいときに見てもらえなくなります。
ホームページ集客のためのデザイン

アクセス数をある程度、増加させることができたら、その次は離脱させないことが重要です。離脱とはアクセスしたホームページからユーザーが別の商品やサービスのホームページへと離れることです。
手を尽くしてアクセスしてもらったユーザーには離脱せずに問い合わせや購入までなんとか至らせたい。そんなときに配慮すべきなのがデザイン性です。
ここでいうデザインとは“ かっこいい ”とか“ スタイリッシュ ”などといった芸術的センスを指すのではありません。閲覧と閲覧のための操作が心地よくスムーズである点です。
ホームページのCTA( コールトゥアクション )

CTAはホームページ上で次の行動に移しやすいボタンやメニューバー、サイドバーを指しています。これらをユーザーに分かりやすく表示して行動してもらうことです。
「 この商品ってどこの会社が作っているのだろう 」
「 実際に購入したお客様の声が知りたいな 」
そんな風にユーザーが考えた際、それをすぐに行動に移せるレイアウトになっているでしょうか。ユーザーを迷わせていませんか。
ユーザーが次の行動に移りやすい、それが使い勝手の良さであり、ホームページ集客におけるデザインの正しさです。ユーザーを親切に、エスコートできているかを考えてみましょう。
デザインが良いだけになっているホームページ
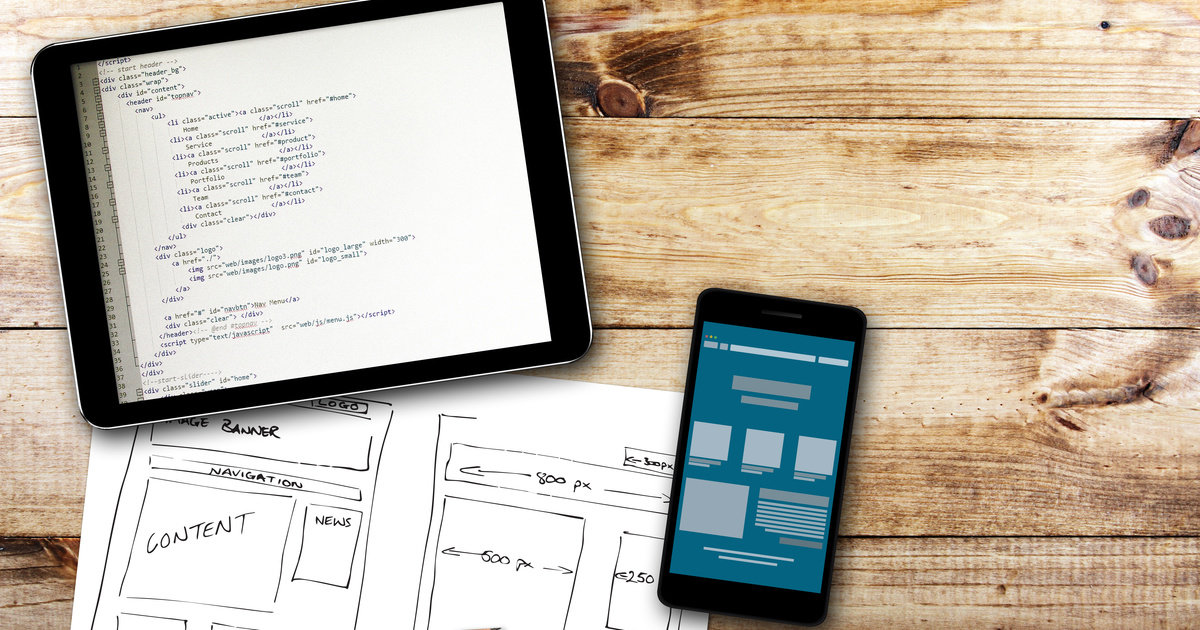
あなたのホームページではパッと見のカッコよさ、美しさが重視されていないでしょうか。デザインの良さだけになっていないかどうか、以下の項目でチェックしてみてください。
- 読み込みの速度でユーザーをイライラさせていませんか
- 読みやすいフォントと色で書かれていますか
- 文字が背景に溶け込み読みづらいことはありませんか
- 字間と行間は読みやすく整えられていますか
- 視認性が高く解像度が十分な画像を用いていますか
- 理解しやすいレイアウトですか
- ユーザーが価値と感じられる充実したコンテンツが用意されていますか
ホームページ集客におけるデザインのポイントは、ユーザーにとって、ホームページ閲覧が満足するものかどうかです。
ユーザビリティが高ければ、相乗効果としてホームページ自体のSEO効果も高めることになります。
ホームページ集客のコツ

ホームページ集客に取り組むにあたって、目を離さないでほしい数値は「 ページビュー数 」「 直帰率 」「 離脱率 」の3つです。
なぜならページビュー数を伸ばし、直帰率を下げ、離脱率が減れば集客は成功といえるからです。
もうひとつのポイントがキーワード選定。ホームページにてメインで訴えるキーワードやSEO対策でのキーワード、WEB広告においても検索キーワードという題材について説明しました。
つまりホームページ集客においてはキーワードの選定が大部分の施策に影響を与えているということなのです。
キーワード選定はより多くの人が検索するであろうビックワードにするか、狙いを狭めてスモールワードにするかという判断が難しいとされます。
大きすぎれば競合は増えますし、小さすぎればアクセスを稼ぐにしても、そもそもそのワードに興味をもっている対象が少ないというのが難しさの理由。
そこで実施してみてほしいことはビックワードに加えてスモールワードを設定すること。
2〜3ワードの組み合わせをキーワードにするという手法です。検索数を適度に下げつつも、あなたのホームページの特性の主張を弱めることもありません。
まとめ
ホームページ集客への対策は限られた時間と予算と人員で行う場合がほとんどでしょう。それぞれの手法の強みを理解し効果的に取り組みたいものです。
そこでやはり怠れないのは改善を繰り返すということです。作りっぱなしが最も危険。アクセス数が伸びないからと安易に業者任せのリニューアルを行うのも作りっぱなしの一つです。
作成し、更新したら、それに加えて定期的にアクセス解析を行い、改善点を探ります。トライアルアンドエラーでより良いコンテンツや手法を見つけていきましょう。
